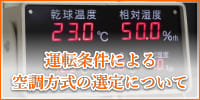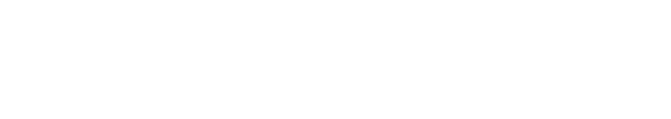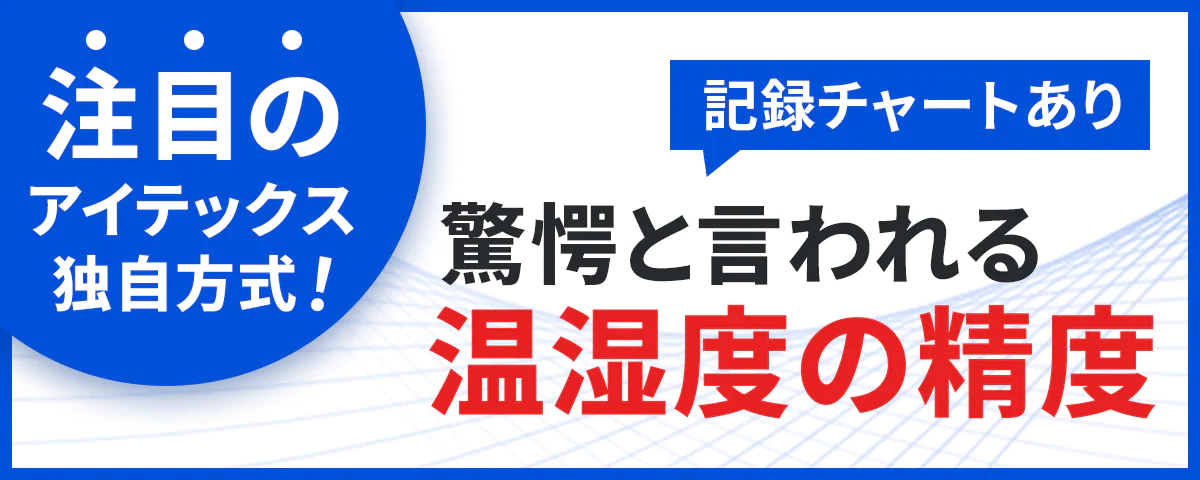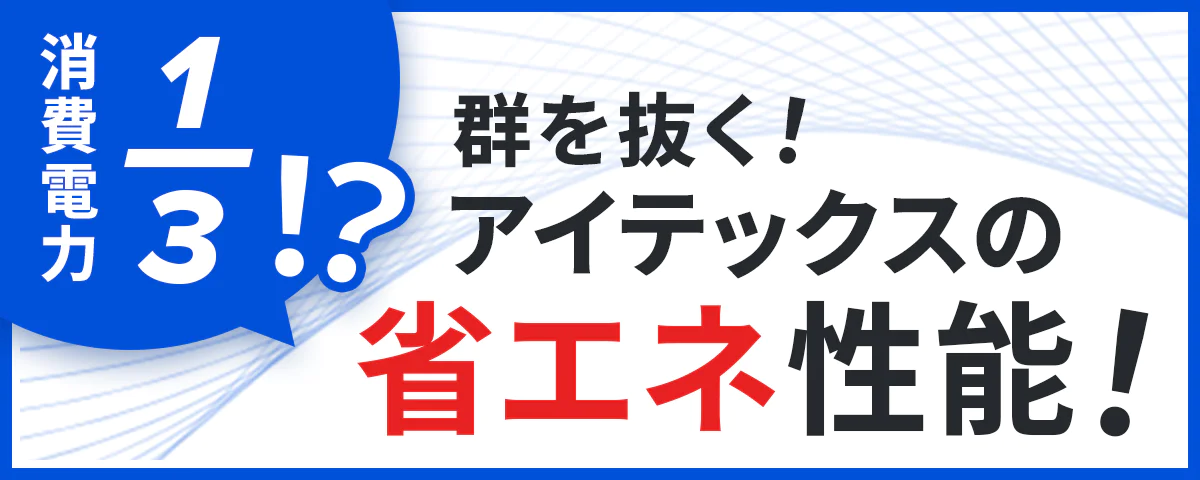試験室の水道使用量
一般的な空調機から弊社のDPC方式やCSC方式の水道使用量について解説します。
試験室の水道使用量
一般的な空調機の水道使用量
一般的な恒温恒湿室や、環境試験室の空調機には、加湿器が使用されております。
加湿器を選定する時は、設計時に、計算値より少し余裕を見ており、恒温恒湿室では4kW程度、環境試験室では、8kW程度が良く使用されております。
一般的な空調方式は、PID方式が多く、これはエアコン等で、空気を冷却除湿して、低下した温度と湿度を加熱ヒーターと、加湿器で上昇させて、設定値で安定に保持させる方式です。
エアコンの能力選定は、夏季の最大熱負荷を想定し、安全率として1.1~1.2を掛けて算出しています。加熱ヒーターは、最大冷却量と同じ程度に選定して、加湿器は、概ね、その1/3~半分程度の容量になっている例が多く見られます。
冬季は外気の湿度が低下しますが、PID方式は、冬季でも冷却除湿していますから、冬季の再加熱量と加湿量は、夏季よりかなり大きくなり、電気料金が高くなる欠点が有ります。
容量的に、冬季の加湿能力は、ギリギリと言った空調機が良く有ります。加湿器の稼働率が高いと言う事は、冬季は加湿器の故障にも悩まされる事になります。
年間を平均して見ると、加湿器は、選定された容量の概ね半分程度の能力で働く様になります。電熱式の加湿器から蒸発する水量は、加湿器の構造にもよりますが、概ね1kW当たり、1.2~1.3ℓ程度です。
小型の恒温恒湿室では、良く4kW程度の加湿器が使用されており、これが半分程度働いて、年間平均で、概ね2kW消費していたとすると、消費水量は1時間で、2.6ℓになります。
24時間では、62.4ℓ、1年間では、22776ℓですから、何とこの小さな恒温恒湿室でも、1年間では、22.8tもの水道水を消費する事になります。
水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル分は微量ですが、蒸発しないので、加湿器の中に残ります。この様に消費水量が多ければ、微量とは言え、加湿器の内部にミネラルが蓄積しますから、これが加湿器トラブルの大きな原因になっています。
一般的な空調機では、冬季で外気が乾燥している時でも、加湿器は働いております。冷却コイルは、冬季には必要の無い除湿しており、ポタポタと水滴が落ちるのが確認できます。
この水滴は、蒸留水なのです。このPID方式の空調機では、製造するのにはエネルギーとお金のかかる蒸留水をどんどん作り出して、水滴にして捨ててしまっているのです。
加湿器の故障を防止する為に、純水器を薦められますが、純水器を使用すると、この高価な純水を加湿器で蒸発させて、冷却コイルで除湿して、蒸留水にして、捨ててしまいます。
これだけの水量ですと、純水器の保守費用は驚くほど高額になります。
これらの詳細は、技術資料の、軟水器と加湿器の資料をご参照下さい。
弊社DPC方式の空調機は、夏季は1滴の水も消費しません。
夏季には水道水を一滴も消費しない等と言うと、どなたも信用しません。この様な事を言うアイテックスは、詐欺師だと思われています。
それは、他の方式の空調機では、加湿器を使用しますので、必ず水道水が必要だからです。
一般的な空調業界では、水を消費しない空調機など、ある筈が無いと思われています。
また、加湿器がトラブルを起こすと、加湿器の故障防止には、純水器が有効だと言われて、純水器を採用している例が多く有ります。すると、今度は、高価な純水を大量に消費するので、とても困っているのが実情です。
純水器と加湿器の保守には高額な費用がかかるので、加湿器の使用をやめて、恒温恒湿室をやむなく、ただの恒温室として使用している例は、数多くお見受けします。
そんな水を消費しない夢の様な空調機が有るのに、ウチでは、何でこんなに純水に経費が掛かり、加湿器故障で苦労しているのだと考えれば、水を消費しない空調機が有るなんて、これは詐欺だろうと思われても、仕方のない事だと思います。
弊社独自のDPC方式の動作原理
DPC方式は、一定の水温に保った冷水で除湿と加湿をする方式です。冷水の温度を一定に保って、室内の循環空気と接触させると、冬季は冷水が自然に蒸発して加湿を行います。
夏季は循環空気が冷水に触れると、自然に凝縮して除湿します。
DPC方式は、状況に応じて、水温を自動制御していますので、年間を通して、極めて安定した温湿度を得る事が出来ます。
精度にご興味があれば、技術資料の、驚愕と言われる温湿度の精度をご覧ください。
夏季に温湿度の高い空気を冷却水に接触させると、冷水に触れた空気は凝縮して水になるので、結果的に除湿されます。水槽内の冷却水は、凝縮水が加わって、自然に増加します。
水位の上がった冷水は、オーバーフローされて、水槽内は常時満水の状態に保たれますから、基本的に夏季は水道水を一滴も使わないのです。空気中の水分だけで運転しています。
エアフィルタを通せば、空気中の水分を凝縮した結露水は、ほぼ蒸留水であると言えます。蒸留水で空調機内の水槽の水は自然に置換されますから、何時でも、空調機内部の冷却水は、透明で、清潔な状態を保ちます。
他社製品を弊社DPC方式に入替たお客様の例
他社のエアコンと加湿器を使用した空調機を、弊社のDPC方式に入れ替えしたお客様がおられます。この装置は、年間で純水を5tも消費していたそうです。その純水器にかかる経費が社内でも、大きな問題になっていたそうです。
弊社の空調機は、純水器は不要だし、消費する水道水も、無駄が無いので、とても少ないと説明しましたが、なかなか信じていただけず、これを実証する為に水道メーターを取付けしました。3月の納入で、6ヵ月後の9月に、お客様が水道メーターを確認したら、、たったの200ℓしか消費しておらず、家庭のお風呂1杯分しか水道水を消費していなかった事に、大変驚かれていました。
この200ℓは、3~5月に消費した物で、6~9月には、ほとんど消費していなかったと想定されます。年間で考えても、水道水は、数百ℓしか消費しません。
DPC方式の消費水量が極めて少ない理由
夏季は外気の温湿度が、30℃/60%RH以上になりますが、30℃/60%の空気の露点温度は、21.4℃です。
DPC方式の空調機の内部では、10℃程度の冷水が散水されております。室内の循環空気が、この冷却水に触れると、凝縮して、水に替わります。この水で水槽内の冷却水は、自然増加するので、オーバーフローされて、冷却水は、自然に置換されています。
空気は、エアフィルタを通るので、この水はほぼ蒸留水なのです。
外気の温湿度が高い程、置換する水量は多くなりますので、空調機の内部は、いつでも綺麗に保たれるのです。
この様に、夏季は、冷却水が自然に増加するので、一滴の水道水も消費しません。
季節が変わり、外気の温湿度が20℃/50%RHになったと仮定します。この空気の露点温度は、約10℃になります。この状態の時の10℃の冷却水は、温度を下げているだけです。ここを通過して多湿になった空気を23℃迄加熱すれば、湿度が低下して、50%の相対湿度が得られます。この季節の空調機の内部では、除湿も加湿もしていません。
但し、冷却水は、循環空気と接触していますから、汚れて来ます。この為、定時的に水道水と置換して、水槽内の冷却水の水質が低下する事を防止しています。
この時の水道水の消費量は、1日に、10~20ℓ程度です。
冬になると、外気の温湿度が低下します。外気の露点温度が、10℃以下になると、冷却水の温度の方が高くなりますから、ここで初めて、冷却水が蒸発を始めて、加湿が始まります。
外気の相対湿度が低い程、湿度の差が大きくなり、加湿量は自然に増加して行きます。
相対湿度が設定値の50%より上昇しそうになると、冷却水の冷却量を増やして、蒸発量を減少させます。冷水温度を50%に保つ様に精密に制御すれば、過剰な加湿は起きません。
結果的に、驚愕と言われる程の極めて安定した湿度を得る事が出来るのです。
他の空調方式では、冬季でも、冷却コイルから、常時、蒸留水のドレンがポタポタ流れ出るような無駄な加湿を行いますが、DPC方式は、冬季でも、必要以上の加湿をしないので、1滴のドレンも発生しません。冬季でも消費水量は少なく、概ね、10~20ℓ程度になります。
但し、冷却水を置換する為に、定時的に数ℓの排水置換を行いますが、この排水量と合わせても、1日で30~40ℓ程度です。
DPC方式は、一般家庭の水道使用量より、はるかに少ない量で運転が可能です。
また、DPC方式は、加湿器方式の様に、水を沸騰させないので、純水器を使用する必要は有りません。水道水は単価が非常に安いので、水道料金の心配をする必要も有りません。
また、井戸水や、工業用水で運転されている例も有ります。あらかじめ、設置場所に水道水が無い事を連絡して頂ければ、その対策をしますので、井戸水で運転する事も可能です。
加湿器方式は無理ですが、DPC方式は、井戸水でも大きな問題は出ておりません。
ここまで説明しても、他の業者に相談したら、そんな夢の様な話はあり得ないし、聞いた事も無いから、嘘だと言われる様で、初めてのお客様には信用して頂けません。
いくら説明をしても、詐欺師と見られる様で、この話は、なかなか納得して頂けません。
弊社CSC方式の消費水量
弊社DPC方式は、冷水で空気を直接制御するので、低温運転は凍結するので出来ません。
運転範囲が低温から高温多湿迄、広い場合には、弊社CSC方式をお薦めしています。
CSC方式は加湿器を使用する方式ですが、冷却、加熱、除湿、加湿の4信号を同時に制御して、出来るだけ省エネになる様に運転するものです。
冬季は、除湿量を最小に絞りますから、加湿器の稼働率が低くなり、冬季でも加湿器の消費電力は大きくなりません。
加湿器は2台併用が標準で、これを運転中に、湿度を乱さずに、交互に洗浄しています。
CSC方式は加湿器の稼働率が低く、夏季は加湿器を使用しなくても、精密な除湿運転だけで、安定した湿度で運転する事が可能です。これは究極の省エネ運転になります。
また、加湿器1台が故障しても、残る1台だけで湿度の保持が可能ですから、連続実験中に加湿器が故障しても、何ら実験に影響しません。それでも、加湿器のトラブルは多いので、加湿器の新品交換は、お客様でも簡単に出来る様に工夫されております。
CSC方式は、設定条件を得るのに、必要なだけしか冷却除湿しないので、加熱量と加湿量も少なくなります。最大加熱量と、最大加湿量は、手動ボリウムで絞る事が出来ますので、これを調整すると、従来の装置の、1/3~1/6程度の水道使用量に抑える事が可能です。
省エネモード運転では、精度は少し落ちますが、1/10程度に削減している実績も有ります。
この様な説明をすると、他社の装置と性能差があまり有り過ぎて、信じて頂けないどころか、他社に相談したら、業界大手でも出来ないそんな装置を、零細業のアイテックスに出来る筈がない、そんな事はあり得ない話だから嘘だと言われる様で、詐欺師扱いされます。
そこで弊社では、実際にこれらの性能を見て頂く為に、川口工場に、ショールームを設けてDPC方式と、CSC方式の2機種を公開しております。 ここで実際に、省エネ性、精度、静粛性、メンテナンスのし易さ等を見ていただけます。
ホームページに、ショールームのページが有りますので、詳細は、こちらをご覧ください。
ショールームは何時でもご覧いただけます。百聞は一見に如かずと言いますが、見学して頂ければ、その性能差は直ぐにご確認いただけます。
一抹の不安が有り、ここまで確認に来られて、納得されて、直ぐに内示を頂いたお客様もおられます。
また、この装置は、レンタルとして、ご使用いただく事も可能です。
レンタルと言っても、お部屋の移動は出来ませんので、来所して頂いてのご利用になります。
尚、文中のDPC方式や、CSC方式と言うのは、弊社の社内名称です。他の業者に相談されても、何の事か判りません。これらの詳細も、技術資料で説明しております。ご参照下さい。