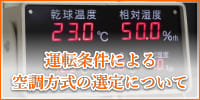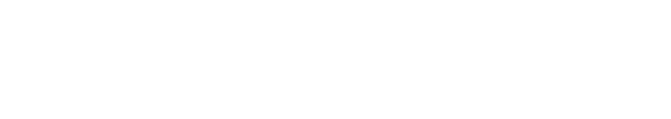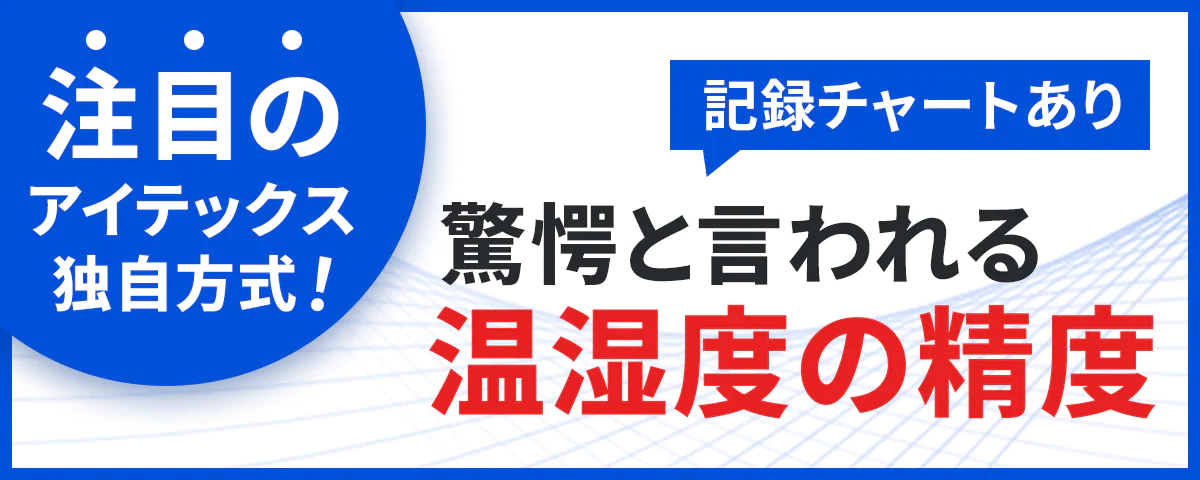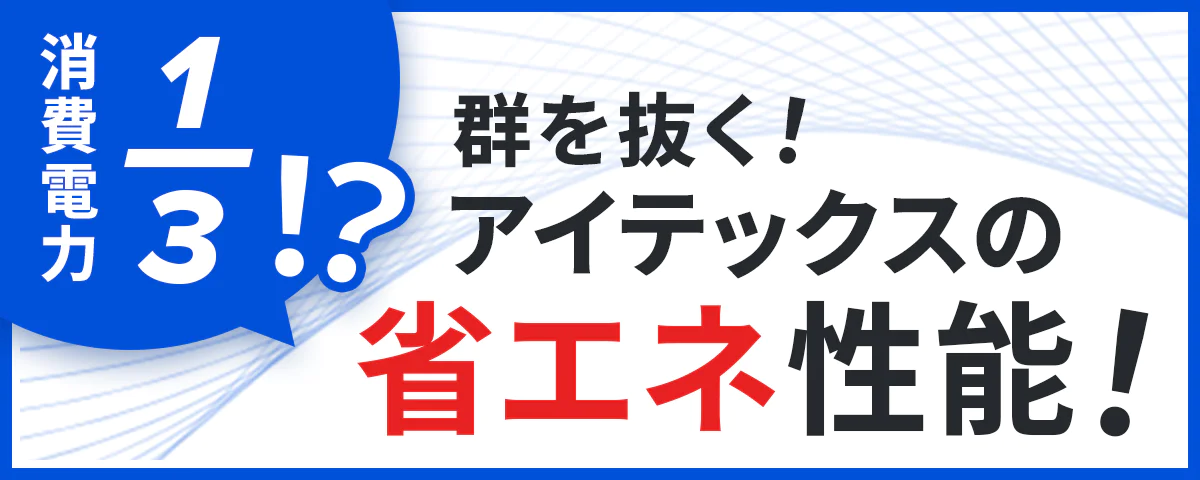カビが生える試験室
カビの原因には、壁に生じる結露などがあります。
カビが生える試験室
運転中の試験室にカビが生えた例は聞きませんが、停止中の試験室ではカビが生える事が有ります。
空調方式によっては、運転中の空調機の中にカビが生えて、室内がカビ臭くなる物がります。
停止中の試験室にカビが発生する原因
恒温恒湿室は、20℃/68% か、23℃/50%で運転されている例が多く有ります。
この時、室内側の壁の表面温度は、20℃か、23℃になっております。
この日は暑くて、試験室の周囲の温湿度が、32℃/70%あったと仮定します。この空気の露点温度は、約26℃です。この空気が、26℃以下の壁に接触すると、その表面では、結露が発生して、水滴が発生します。この結露が発生する境目の温度を露点温度と呼びます。
この暑い日に恒温恒湿室の運転を停止して、そのまま放置すると、この外気は、室内に侵入して来ます。扉が閉じられているから、外気は入らないと考えたくなりますが、ビニールの袋に密閉された焼き海苔が、放置すると直ぐにフニャフニャになり、くっついてしまうのを経験されていると思いますが、湿気は、どんな小さな隙間でも浸透するのです。
露点温度26℃の空気が、室内に侵入して、20℃や、23℃の低い温度の壁に接触すれば、必ずここに結露して水滴になります。この時の室内の相対湿度は、100%なのです。
この為、扉を閉じたまま停止すると、室内の空気の湿度は、必ず上昇します。
空調を止めた恒温恒湿室の室内は、やがて温度も自然に上昇して来て、外気の温度に近くなりますが、室内に水滴が有る為に、室内は、外気より多湿の状態になったままになります。
これが夏季に運転を止めて、扉を閉じておくと、室内にカビか発生する原因になります。
カビは、60%以上の環境を好み、温度が高いほど繁殖のスピードが上がります。
環境試験室では、低温運転や、高温多湿運転が行われますが、低温運転を行ってそのままで停止すれば、壁は低温になっていますから、結露が発生して、びしょびしょになります。
高温多湿運転では、停止すると、室内の温度が下り、相対湿度が上昇して来ます。壁の温度が下って来ると、これも激しい結露の原因になります。
解決方法は、恒温恒湿室を連続で運転するか、運転を止めるなら、扉を解放する事です。
弊社の恒温恒湿室はとても省エネなので、ほとんどが、年間を連続運転されています。
環境試験室では、扉を解放する他に、加湿器を止め、設定温度を外気の温度付近に設定し、常温付近に戻してから停止する方法も有ります。
空調機の内部に発生するカビ
環境試験室は、空調機の内部に冷却コイルが有り、除湿していますから、表面は、凍結しているか、水滴が付着しています。
運転を停止すると、冷却コイルは濡れたままになりますから、これもカビの原因になります。
冷凍機の運転を止めて、送風機だけ運転すれば、冷却コイルは乾燥しますから、乾燥させた後に停止させれば、空調機内部の冷却コイルにも、カビは発生しません。
実際には、環境試験室の運転は、カビ菌にとってはかなり過酷なので、死滅する様です。
冷却コイルが濡れたままで、長期間放置しない限り、カビは繁殖していません。
他社製品で発生するカビ
恒温恒湿室では、比較的価格の安いパッケージエアコンが使用されている例が多く、改造用の部品も販売されておりますので、パッケージエアコンを利用する業者は多く見られます。
パッケージエアコンは、着霜防止の為に、冷却コイルは、プラスの温度域で使用しますから、カビ菌が死滅しません。運転停止を繰返すと、カビが発生する事が有ります
恒温恒湿室には、露点散水方式と呼ばれる機種も有ります。これは冷水を使用して冷却除湿するする方式ですが、空調機の内部に充填剤が有り、連続運転していても、充填剤にカビが生えるので、室内がカビ臭くなる欠点が有ります。
定期的に高額な充填剤を交換する必要が有りますが、交換しても、またすぐにカビが生えてしまいます。省エネな空調機ですが、納入先では、カビ臭さが問題になっております。
この詳細は、各種技術資料の、露点散水方式で説明しておりますので、ご参照下さい。
弊社には、これと基本原理は同じですが、精度が高く、故障が少なく、特に省エネで、カビが生えない、DPC方式の恒温恒湿室が有ります。
こちらも技術資料で詳細に説明しておりますので、ご興味のある方は、参考にされて下さい。