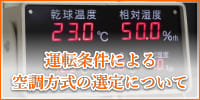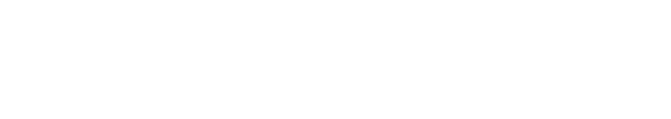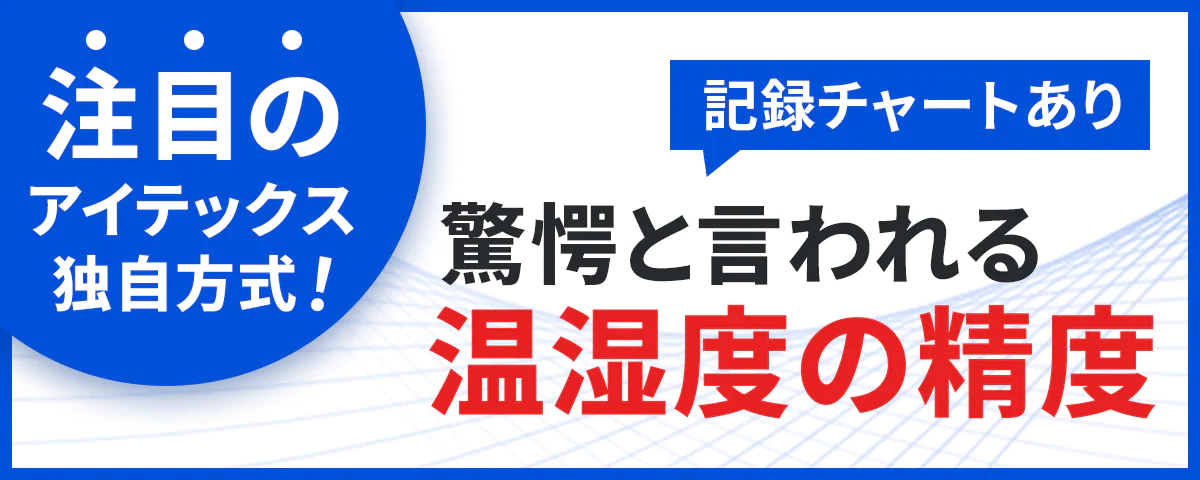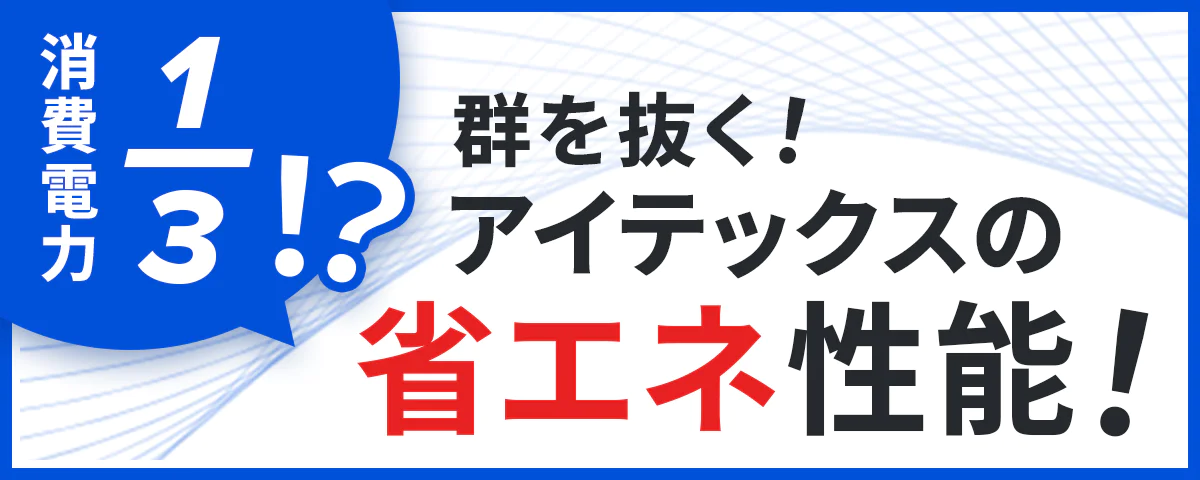水冷と空冷冷凍機
水冷式と空冷式、
それぞれの冷凍機の特徴について説明します。
水冷と空冷冷凍機
冷凍機には水冷式と空冷式が有り、それぞれ、下記の様な特徴が有ります。
水冷式冷凍機
大型の冷凍機は、発熱量が大きいので、水冷式の冷凍機が多く、クーリングタワーが良く使用されております。
小型の水冷式冷凍機も、販売されておりますが、クーリングタワーの管理が大変なので、小型の冷凍機単体の場合は、ほとんどクーリングタワーは使用されなくなりました。
クーリングタワーは、冬季に運転を停止すれば、凍結しますし、夏季にどんどん水を蒸発させれば、蒸発出来ないミネラル分が固形化して蓄積する事や、外気の汚れが入り込むので、定期的な清掃や、メンテナンスが必要で、これを怠ると、かなりトラブルの発生率が高くなる部品です。
冷凍機は、冷媒を使った熱交換機ですから、冷媒管の距離を長くすると、色々な問題を起こします。建物の構造や、美観等の問題で、周囲に何も無いスマートな建物ですと、何処にも空冷式の冷凍機を置く場所が無い場合も有ります。特にテナントのビルでは冷凍機の置き場所や配管ルートが問題になります。
こんな場合には、冷却水の配管であれば長く伸ばせますから、水冷の冷凍機を使用する場合が有ります。
工場や、最初から研究用に建てられた建物の中には、水冷用の冷却水配管が有る場合が有り、この場合は、この配管から分岐させる事が出来ます。
また、井戸水や、工業用水はコストが安いので、垂れ流しで冷却している例も有ります。
屋外に空冷冷凍機の置き場所が無く、井戸水も工業用水も無くて、やむなく水道水で冷却している例も有ります。この場合は、制水弁を取付けて、冷却水の水量を、出来るだけ少なくなる様にギリギリの冷媒圧力で管理しますが、夏季は水道水の温度も上昇しますから、使用量が増えますので、水道水の使い捨ては、あまり経済的な方法ではありません。
また、水冷の冷凍機は、空調機の隣に設置する事が出来ますが、冷凍機はコンプレッサですから、振動と騒音を出します。機械室があれば問題ありませんが、静かな場所や、昼夜運転ですと、夜間になると、騒音が気になる場合が有ります。
下の写真は、病院内の診察室に設置した例ですが、水冷冷凍機本体を、防音BOX 内に収納して、防振防音した例です。深夜になる迄、運転音は聞こえません。

水冷冷凍機を防音して、
室内に設置した例

水冷式冷凍機本体

防音BOXの内部
空冷式冷凍機
水冷式冷凍機の場合は、クーリングタワーや、冷却水設備が必要で、設備の新設や、その後の保守を考慮すると、あまり経済的ではありません。
そこで、現在では、20~50馬力と言った、エアコンや冷凍機でも、空冷式が多くなり、クーリングタワーを見る機会が少なくなりました。
空冷冷凍機は、防水仕様ですから、丸ごと水洗いする事が出来て、メンテナンスにも手間がかかりません。
問題点は、室内の空調機と、屋外の冷凍機の間は、冷媒管で接続しますから、あまり距離が伸ばせません。また、大きなレシプロ式冷凍機なら、高低差も、あまり問題になりませんが、小さなロータリーコンプレッサのインバータ制御では、最低周波数の運転では、長い距離や、大きな高低差があると、冷媒が引ききれない場合や、オイルが戻り難くなる場合が有ります。
下の写真は、実際にインバータ冷凍機を設置した例です。

小型の冷凍機を
10台屋上に設置した例です。

小型と中型を地上に設置した例です。

大型の冷凍機3台の設置例です。
弊社では、全て、能力が可変出来るインバータ冷凍機を採用して、省エネ化しておりますが、コンプレッサですから、圧縮時のトルクの関係があり、大きな冷凍機の能力を、極端に落とす事は出来ません。
そこで、運転条件が幅広い場合等では、その条件に合わせて、大小2台の冷凍機に分けて、自動制御したり、複数台の冷凍機を使用して台数制御を行い、何時でも必要最小限度の冷却除湿量にして、省エネ化を図っております。
この方法は、設備費はかかりますが、設置後の電気料金の差額で、連続運転している場合は、1~2年で、この金額差は、回収が出来ております。改造された場合は、これ程迄に、電気料金の削減が出来るのなら、もっと早く改造を行えば良かったと、言われます。