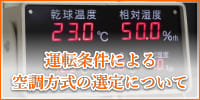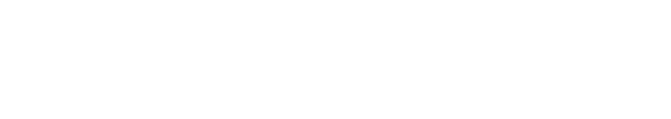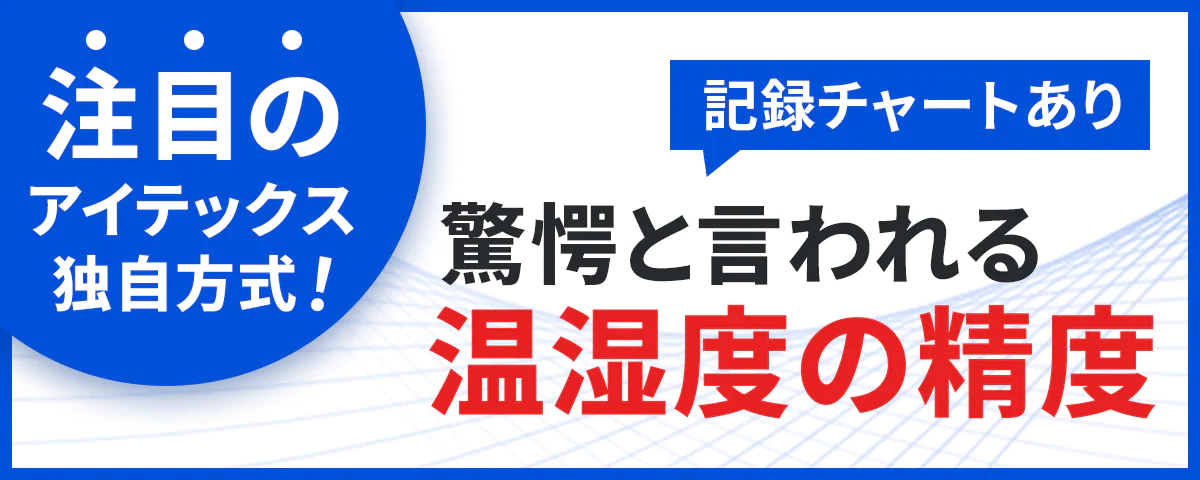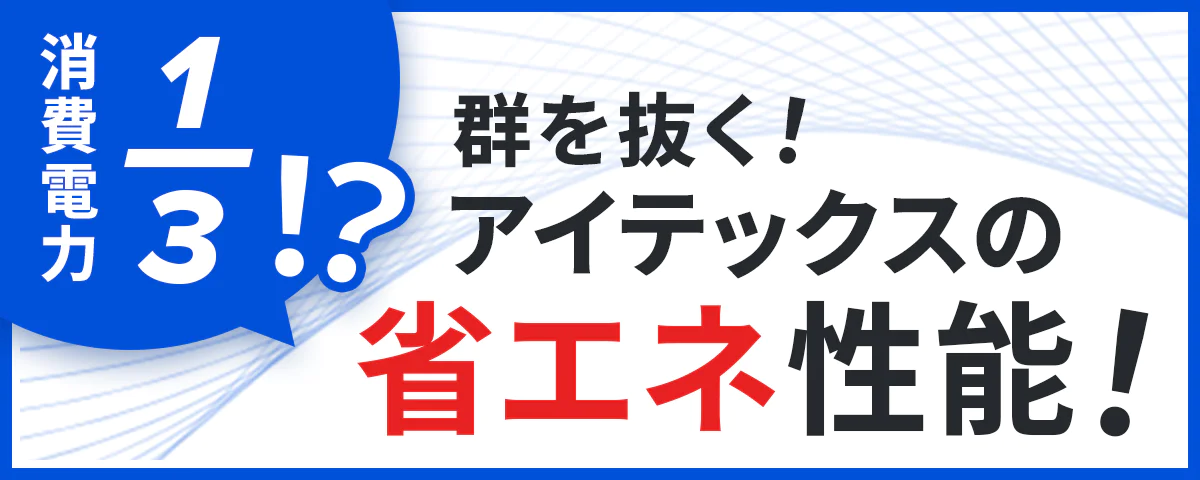冷却コイルの各種霜取方式
冷蔵庫や冷凍庫などにおける、
冷却コイルの霜取方式について解説します。
冷却コイルの各種霜取方式
冷蔵庫の霜取方式
一般的な大型冷蔵庫の運転温度は、+4~5℃付近で運転されている例が多く有ります。
冷蔵庫は、空調機の中の冷却コイルを冷やして、ここに風を流して、冷たくなった空気を、室内に循環しています。
冷蔵庫では、冷却コイルの銅管の内部で冷媒を蒸発させて、−10℃程度の低温を得ており、+4℃の運転でも、コイルの表面温度は、マイナスの温度領域になっています。冷蔵庫の扉を開け閉めすると、外気の湿気が入り込みますが、この空気がマイナス温度の冷却フィンに触れると、水分は霜になり、この着霜を放置すると、やがて透明の固い氷になります。
冷蔵庫の様な低温の装置では、必ず定時的に霜取をする必要が有ります。
冷蔵庫は、換気はしていませんが、扉の開け閉めが多いと、着霜も多くなります。
冷蔵庫は、価格的に安いので、霜取は、単純なオフサイクル霜取方式が使用されております。
これは、運転中に冷凍機だけしばらく停止させ、室内の循環空気の熱で、霜取をする方法です。停止中の冷蔵庫内の温度はすこしずつ上昇して来ます。冷却フィンの霜は水滴に替わり、ここから蒸発しますから、自然加湿しているのと同じで、霜取中の室内の相対湿度は急上昇して、100%近くまで上昇します。
冷蔵庫で低温実験をされている例が良く有りますが、換気は有りません。かなり多湿になりますから、冷蔵庫の中で積み重ねた段ボール箱は潰れ、ノートに鉛筆で文字は書けません。
冷却コイルからは、水滴がポタポタ落ちていますから、冷蔵庫の中の湿度は低いと思われている方が多いのですが、これは絶対湿度が低いのであって、相対湿度は高いのです。
価格が安いからと、大型の冷蔵庫を購入して、低温実験されている例は多いのですが、実際にはこの様な問題があり、困っておられるのが実情です。
冷凍庫の霜取方式
マイナスの温度で運転する冷蔵庫は、冷凍庫と呼んで、冷蔵庫と区別しています。冷凍庫では、着霜がさらに激しくなります。冷蔵庫の様に、冷凍機の運転を停止しても、お部屋がマイナスの温度ですから、絶対に霜は取れません。
この場合は、電気ヒーターやホットガスを使用して除霜する例が多く、霜取中は、送風機も停止させて霜を取ります。
閉鎖された空調機なら良いのですが、価格を下げる為に、冷凍庫用のファンコイルを天井に吊って使用した場合は、ファンコイルには断熱が無いので、霜取中に霜取ヒーターの熱で、室内温度が、プラスの領域に入ってしまう物が有ります。
わずかな時間でも、冷凍庫がプラスの温度になる様では、冷凍庫とは呼べません。
冷凍庫を低温実験室として使用したいと言うご要望も有りますので、弊社では、ファンコイル方式の場合は、霜取中の冷却コイルをダンパーで閉鎖して、霜取ヒーターの熱が室内に入らない様に工夫しております。また、霜取後の再運転は、十分に冷却コイルを冷やしてから行う様にしております。
ファンコイル方式は価格的には安く出来ますが、室内に大きなユニットが下り、風が強く、音がとてもうるさい欠点が有ります。
冷凍庫を実験室として利用するのには、少し無理が有ると思います。
環境試験室の一般的な霜取方式
運転温度が+20~25℃で、湿度50~65%付近の、常温常湿で運転を行う試験室は、一般的に恒温恒湿室と呼んでおります。この温湿度域では、冷却コイルに着霜は発生しません。
実際に着霜するのは、概ね+15℃以下で、温度が+20℃であっても、湿度を40%以下に設定すると、冷却コイルがマイナスの温度になり、着霜します。この付近の温湿度条件が、着霜するかしないかの限界点になります。
恒温恒湿室が着霜したらクレームになりますから、運転可能な温湿度には余裕を見ており、最低温度が20℃以上で、湿度は50%以上としております。
エアコンの設定目盛りには、+18℃以下が有りませんが、この温度以下では、冷却コイルに着霜する可能性が有るからで、エアコンには霜取回路が無いので、これが標準の仕様です。
+20℃以下の運転や、40%以下の低湿度の運転、高温多湿等の運転が可能な試験室は、弊社では、環境試験室と言う呼び名で区別しております。
環境試験室で、+15℃以下や、常温でも低湿度の運転を行うと、デストリビュータや、冷却コイルの端の方から、少しずつ着霜が発生します。
連続で運転すると、この霜が成長して、やがて冷却コイル全体が目詰まりを起こします。
すると運転していた低温低湿度の状態から、湿度が上昇して不安定になり始め、やがて温度も上昇して来て、不安定になります。
着霜を放置すると、冷却コイル内で蒸発しきれなかった冷媒は、液の状態で冷凍機に戻ります。液は圧縮できませんので、これは冷凍機が重故障を起こす原因になります。
冷蔵庫や冷凍庫は、人が連続で入室する事は想定していませんので、換気はしておりません。それでも1日に数回の霜取は必要で、運転を定時的に停止して霜取を行う必要があります。環境試験室で、常時入室者が居る想定では、常に外気が導入出来る構造にしています。
低温状態で換気すると、特に外気湿度の高い夏季は、短時間で冷却コイルに霜が蓄積します。
連続で低温運転すると、霜は成長して凍結し、氷の状態になります。こうなると、霜取時間がとても長くなります。冷蔵庫の様に運転を休止して霜取を行う方法では、この間に室内の温湿度は必ず上昇してしまいます。環境試験室でも、一般的には冷蔵庫と同じ霜取方式にしている物が多く有ります。この場合は、室内に発熱する機器があると、霜取中に温湿度が急上昇しますので、注意が必要です。
また、霜取の為に運転を停止する場合は、換気も停止させております。換気を行ったままで運転を停止すると、湿度の高い外気が冷たい室内の壁や什器に触れるので、必ず結露します。室内の壁や什器の表面は、一瞬で結露して、びしょ濡れの状態になってしまいます。
低温で連続運転中に、外気が入ると、冷却コイルには着霜が発生します。着霜すると、冷凍機は連続で運転しているのに、温湿度が次第に上昇して来て、下がらなくなります。
この為に、夏季の冷蔵庫では、4時間運程度運転すると、運転を中止して、30分程度の霜取りを行っています。
この様な霜取方式では、霜取中に室内の温湿度が上昇して、室内の相対湿度は100%になる事が有ります。室内に結露が発生した状態で霜取から復帰すると、この結露が完全に取れて、元の低温状態に戻るのには、更に時間がかかります。
他社の環境試験室では、低温運転が出来ても、霜取回路が無い物を見受ける事が有ります。
この様な空調機では、冷却コイルに着霜が発生した場合は、冷凍機のスイッチだけを切り、高めの温度に設定して運転して、循環空気の熱で除霜する事になります。
但し、完全に透明な氷の状態になるまで凍結させてしまった場合は、これを解凍するのには、この方法では、1日かかる事も有ります。
しかし、これが従来の環境試験室の実情なのです。メーカーのカタログや仕様書には、運転を休止して霜取を行う等、都合の悪い事は、一切記載されておりません。霜取方式が記載されていても、ホットガス方式等と最新技術の様に、さらっと記載されているだけです。
環境試験室を導入して、実際に低温で運転したら、連続で低温運転が出来ない事が判ります。
そして霜取時には、室内の温湿度が急上昇して結露する事等が判明すると、想定していた連続の低温低湿の状態とは全く異なる実験結果になります。この様な装置では、冬季を想定した低温低湿度の試験は出来ません。低温で連続運転が可能な機種が必要です。
冷蔵庫と同じ定時霜取方式では、扉を解放していた等の条件が有ると、極端に冷却コイルに着霜して、霜取時間中に霜が取り切れず、霜が次第に蓄積して凍結する事が有ります。
連続で低温運転している場合は、凍結してしまった冷却コイルの氷は、運転を停止しなければ、自然に消える事は絶対に有りません。必ず氷は大きく成長します。
この様な装置でも、一応低温運転はできるのですから、業者は嘘をついておりません。
低温運転では必ず定時的な霜取が必要です。霜取時は温湿度が大幅に上昇します、これを詳しく説明したら、この装置は、低温の連続実験では使い物になりませんと説明している様な物です。霜取に関しては、出来るだけ触れない様にしているとしか思えません。
たとえば、電話帳の様な物は、霜取中に多湿になると、直ぐに吸湿して、紙がフニャフニャになります。運転が復帰して、温湿度が下っても、電話帳の中迄は乾きません。
吸湿性が高く、放湿性が低いからです。この様な現象は他でも見られます。運転の途中で、霜取の為に運転休止したり、霜取中の湿度が制御できない様な試験室では、冬季を想定した精密な低温低湿の試験は出来ません。
また、環境試験室でも、+4℃以下や、マイナスの温度域が有りますと、霜取の方式と断熱が変わりますので、プラスの領域で運転する環境試験室とは、価格が大きく変わって来ます。
この様な状況を考えたら、環境試験室の霜取方式が、冷蔵庫や冷凍庫と同じでは、低温低湿での連続運転試験は満足に出来ません。これは容易に想像ができると思います。
弊社の環境試験室の霜取方式
環境試験室で低温運転を行うには、霜取は絶対に必要です。霜取中には、室内の温湿度が大幅に乱れます。これは実際の気象環境とは大きく異なります。これでは、冬季を想定した精密な連続試験が出来ないので、研究者の皆様が、意外に困っておられる問題なのです。
弊社では、この問題に早くから対処しており、独自のデュアルコイル方式を開発しました。
運転中に着霜した冷却コイルを交互に霜取する方式で、低温でも完全な連続運転が出来て、軽客コイルの切替時にも温湿度が乱れない様に工夫した空調機です。
但し、デュアルコイル方式でも、マイナスの温度で長期間の連続運転は出来ません。
これはマイナスの温度域では、冷却コイル以外の場所にも少しずつ着霜する為で、送風機に着霜すると、ブレードのバランスが崩れて、振動が出たりします。
実験装置の場合は、数日程度の試験が多いので、あまり問題になっておりません。
長期の運転を行う場合は、2台の空調機を交互に運転する様な仕様になりますが、価格は高くなります。
マイナスの温度では、連続で入室しない場合が多く、扉の開閉回数も少ない場合が多いので、実際には、価格が高くなる面も有り、マイナスの温度域では、定時的に運転を休止して霜取する方式が多くなっております。