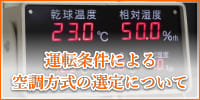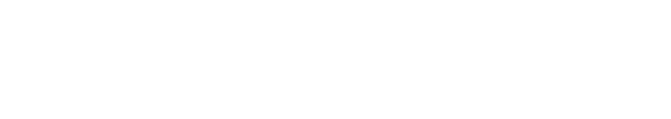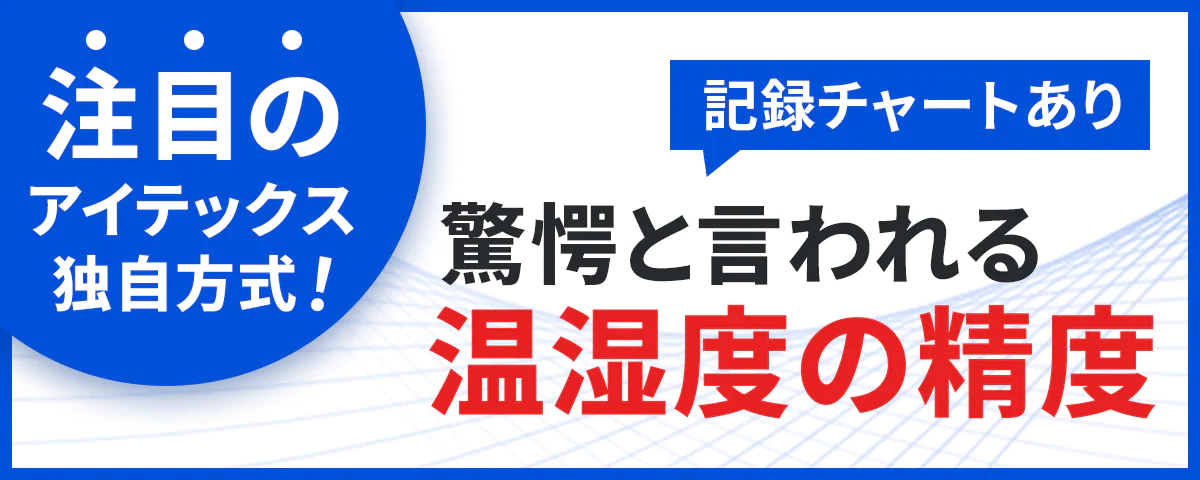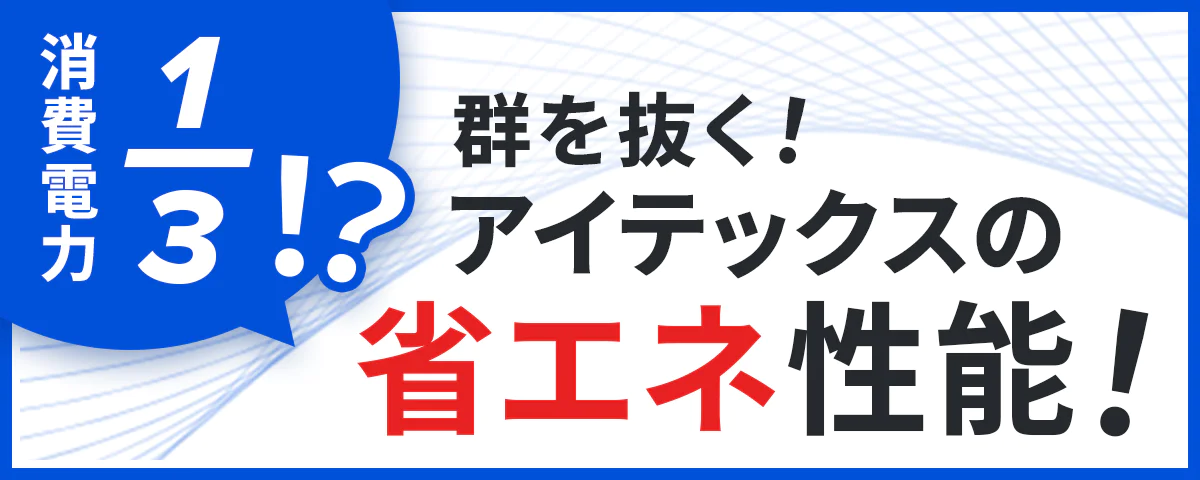ユーティリティ
試験室におけるユーティリティについて解説します。
ユーティリティ
試験室のユーティリティとは
試験室の打ち合わせで、良くユーティリティと言う言葉が出ます。
調べますと、役に立つ事、有益な物、便利な物と有り、意味が少し違うような気もしますが、これは試験室を設置するに当たり、あらかじめお客様が用意する設備を差す業界用語です。
お客様に用意して頂く必要のある物は、平らな設置場所と、屋外の冷凍機置場、電気、水道、床の排水孔等になります。
お部屋の設置場所
プレハブ構造の試験室は、基本的には建物の中に設置する構造です。工場の軒下等の設置例も有ります。10㎡(6畳)以上の試験室を屋外に設置する場合は、建築確認申請が必要になります。屋外に設置する場合は、設置予定の場所に、建築業者に、柱と屋根だけでも良いので、小屋掛けをして頂き、弊社では、その中に設置する様な形になります。
お部屋は基本的には900幅の断熱パネルを使用したプレハブ構造で、幅ほ狭くしたパネルを壁と天井の必要分だけ製作すれば、どの様な半端なサイズでも対応する事が出来ます。
空調機も現場で組立する方式です。本体の幅は600以下で製作できます。設置予定の場所に、片開きの扉が有れば、かなり狭い場所でも、その中に設置する事が出来ます。
設置を希望する事務所、工場等の建築図面か見取図を戴ければ、それに合わせて、出入口の位置と広さ、扉の開く方向、窓の位置、コンセントの位置、空調機と制御盤の位置、排水口の希望位置等を示した計画図を作成します。これを叩き台にして、計画を進めて戴きます。
現場の下見、計画図面の作成、お見積の提出迄は、サービスで行っております。
冷凍機の置場
冷凍機は屋外の設置が基本になります。1階であれば、建物の壁、花壇の一部等に設置する例が多く、2階以上は、使用可能なベランダが有れば、ベランダの設置例も多く有ります。
ビルでは、美観の問題も有り、屋上にしか設置できない例が多く、屋上迄パイプシャフトを通して配管する必要が有ります。
この屋上迄の配管工事は、距離が長くなり、一番冷媒工事の費用がかかります。
近年は夏季の外気温が高くなりましたので、冷凍機は風通しの良い場所に設置する必要があります。狭い場所に押し込むと、夏季にトラブル発生の原因になります。
冷凍機の形状は、写真の家庭用のエアコンと同じ様な形で、少し大きくなります。左側は6畳用のエアコンの室外機で、右側が、0.75kW~2.2kWの冷凍機です。

大きな試験室では、省エネの為にあえて小型の冷凍機を2台使用して、運転台数を運転の条件に合わせて、自動で選択させている例も有ります。この方法は、大きな冷凍機を1台だけ使用するより、冬季の消費電力が低下して、年間の電気料金がとても安くなります。
大きな工場では、広くて天井が高く、風通しが良くて、空調が無い条件等では、工場の内部に冷凍機を設置している例も有ります。
小さな冷凍機では、配管距離が長くなると、効率が悪くなりますので、一般的に、空調機と冷凍機の距離は、最大でも30M以内の位置を選定して下さい。
また、冷凍機の冷媒は、オイルと一緒に循環しているので、空調機より冷凍機の位置が高いと、冷媒が戻り難くなります。逆に、空調機より冷凍機が低い位置に有る場合は、この問題は有りません。この落差は、20M未満が望ましく、試験室が1階で、冷凍機が7階以上の屋上等の例では、小型の冷凍機では、オイル戻りに無理が有ります。
近くにどうしても冷凍機の置き場所が無い場合は、水冷の冷凍機を採用する例も有ります。
建物内に冷却循環水が回っている場合は、これが使用出来ますが、何も無い場合は、水道水に制水弁を取付けて、垂れ流しと言う方法になります。
この方法は、水道が、工業用水や、井戸水の場合はまだ良いのですが、上水を使用する場合は、水道代が高額になる欠点が有ります。
試験室の電源
試験室の空調機には、必ず動力電源と呼ばれる三相200Vの電源が必要になります。この電源容量は、仕様書で確認して、電源容量が無い場合は、あらかじめ電源の新設か増設が必要です。
この外に室内の照明用と、コンセント用の100Vの電源が必要になります。
電源工事は、基本的に、制御盤迄はお客様側の電気工事範囲で、制御盤に3φ200V、分電盤に1φ100Vの電線を接続して頂き、ここを責任の分岐点としております。
工事業者様と日程の調整がつかない場合も多く、実際には、現場の空調機の天井付近に電源ケーブルを必要な長さに巻いて支給して頂き、弊社で接続している例も良く有ります。
電源容量についての詳細は、仕様書の設備電力と消費電力の項目をご参照下さい。
試験室迄の水道
恒温恒湿室や環境試験室では加湿しますから、必ず水道が必要になります。湿度制御しない恒温室や、高温室の場合は、水道は必要有りません。
水道は、空調機の付近に、バルブ止めで支給して頂きます。お客様側の水道工事では、20Aの鉄管が良く使用されています。ここから先は、弊社で配管しますが、弊社の空調機迄の水道配管と、空調機の内部配管は、13Aの耐衝撃塩ビ配管(HIVP)になります。
加湿器は、水を沸かして加湿しますので、井戸水や工業用水は使用出来ません。カルシウム、マグネシウム等のミネラル分が多く、ミネラルは蒸発しないので加湿器の中に残されて、短期間で故障する原因になります。(これをスケールの蓄積と呼んでいます。)
一般的に水道水は軟水と言われますが、地域によっては、原水が井戸水混合の場所が有り、この地域では、水道水であっても、加湿器のスケール蓄積による故障が多発します。
水道水が硬水の場合は、純水器でミネラル分を除去する方法も有りますが、純水の製造と保守には、大きな経費が掛かります。加湿器のメンテナンスが減る代わりに、高額な純水の保守費がかかりますので、この方法は、あまり得策ではありません。
弊社のDPC 方式は、水で除湿と加湿をしますので、スケールの蓄積は有りません。現場に井戸水しか無い場合の恒温恒湿室は、DPC方式を採用して下さい。
DPC方式は井戸水でもトラブルが無く、長期間ご使用いただいている実績が有ります。
弊社のCSC方式の空調機は、内部に2台の加湿器が有り、これを交互に洗浄して使用しております。洗浄中も温湿度は乱れず、スケールの蓄積を大幅に遅らせています。それでも、井戸水を混合している水道水の場合は、短期間でスケールが蓄積しています。
CSC方式も、DPC方式も、弊社独自の空調機ですから、他社にこの名称は有りません。
他社にこの名称で問い合わせしても、何の事かわかりません。
CSCとDPC方式は、弊社のホームページで個別に詳細な説明をしておりますので、こちらも参照にされて見て下さい。
試験室の排水
夏季にエアコンの排水口から、ボタボタと水が出ているのをご覧になった事が有ると思いますが、加湿器の無い恒温室でも、この様に、ドレン排水は必ず出ます。
弊社空調機は、どの方式でも、加湿器の洗浄や、冷却水の置換等を行いますから、エアコンよりは、一時的に多くの排水が発生します。空調機近くには、必ず排水孔が必要になります。
この排水配管は、天井裏のエアコンの配管と共用出来ません。一時的な排水量が多いので、天井から漏水する原因になります。2階以上に試験室を設置する場合の排水ルートは、階下の天吊のエアコンとは別にして下さい。
空調機本体の排水口は、内径25ですが、排水の配管が細いと詰まり易いので、新設する場合は、内径40を指定して下さい。空調機の排水口の高さは、標準でFL150H、高くしても、FL250Hですから、床排水が基本になります。
空調機の排水口には、下水の臭気や、虫などが入らない様に、写真の様なトラップを取付て、逆流を防止しています。

現場に排水孔が無い場合も有りますので、この場合は、写真の様なドレンアップポンプを使用します。
遠方の高い場所にも排水できますが、ドレンポンプのトラブルは、過去に1番多く発生しております。
他に方法が有れば、出来るだけ避けたい方法です。
ポンプの故障信号で、警報を出して空調機は停止させますが、故障警報が出ないで満水になる事があります。

過去にポンプが故障しても警報が出ないで、漏水した事故が、数件発生しております。
テナントのビル等では、階下に漏水すると、大きな責任問題になりますから、どうしてもドレンポンプで排水する必要がある場合は、空調機の周囲に、漏水検知器も設置して、漏水を検知した場合は、空調機の停止だけでなく、給水弁も閉じる対策をお薦めしています。