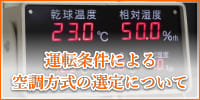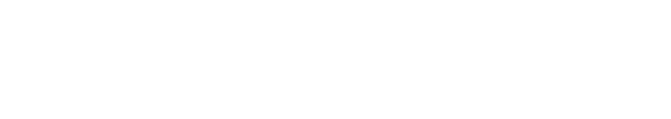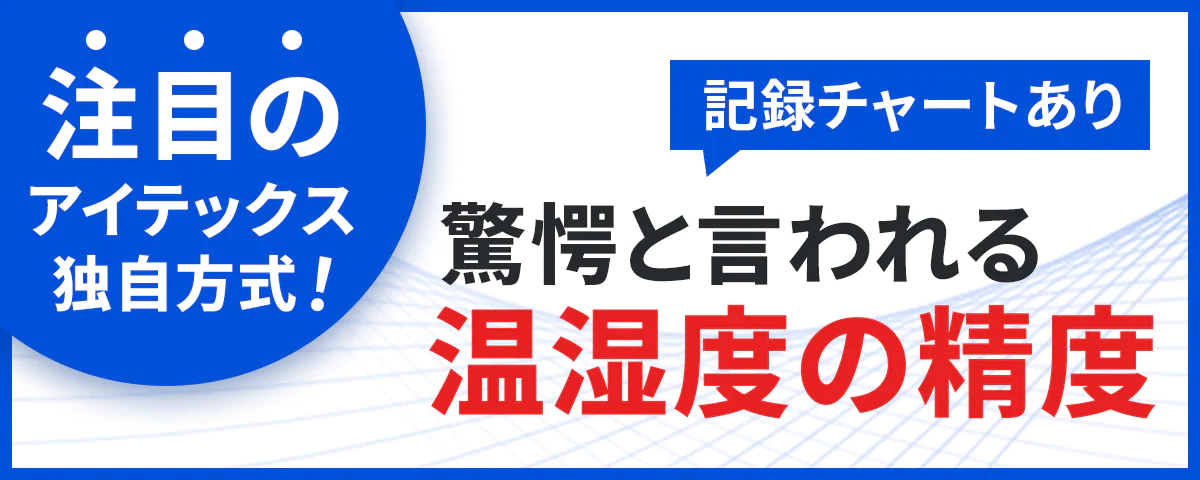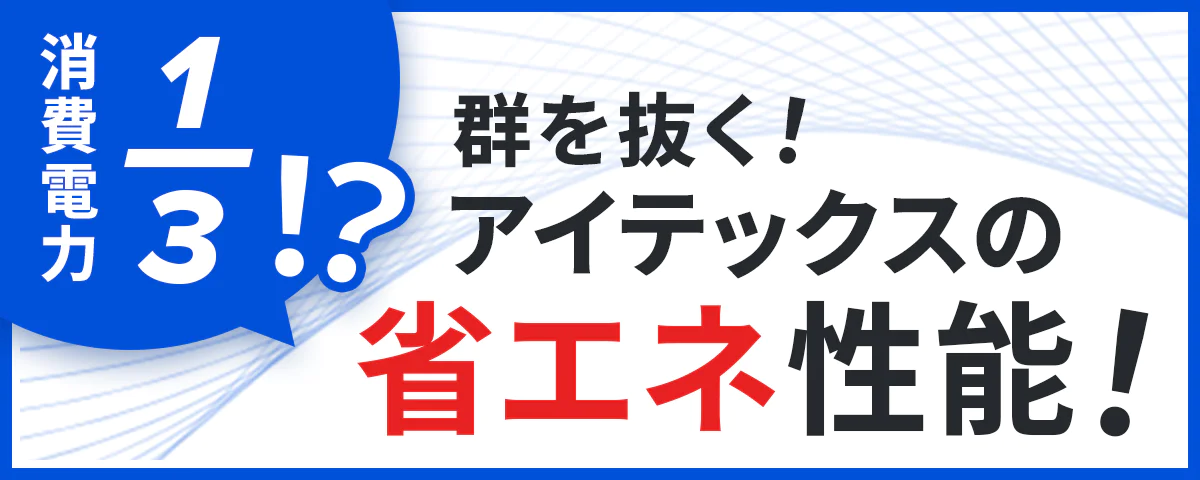試験室の温湿度が下らない
環境試験室の温湿度が下がらない原因について
解説します。
試験室の温湿度が下らない
環境試験室の温湿度が下がらなくなる原因には、主に下記の様な問題が有ります。
-
冷凍機の冷媒ガスが漏洩した。
以前は出ていた低温や低湿度の条件が、だんだん出なくなる原因では1番多い症状です。
弊社の古い装置の冷凍機は、冷媒圧力用の2連のゲージを追加で取付しております。
2019~2020年以降の冷凍機には、冷凍機正面右上に小さな窓が有り、この中にデジタルで、高圧と低圧の、2種類の圧力が表示されております。
旧型機は
アナログゲージを
追加取付
新型機は
小窓の中に
デジタル表示
サイトグラス
このゲージの冷媒圧力が以前より低くなっていると、冷媒漏洩の可能性が有ります。
また、冷凍機の付近の配管に、サイトグラス (リキットアイ) が取付けられており、冷媒が不足すると、ガラスの部分に泡が流れて見えます。満液の場合は、透明です。
温湿度が以前より下がらなくなった場合は、このゲージの圧力とサイトグラスの状態を連絡いただければ、対処ができます。ここに表示される両方の冷媒圧力が低い場合や、サイトグラスに泡が見える場合は、冷媒が漏洩した可能性が有ります。
但し、他社製品で、パッケージエアコンを利用した物は、ゲージが無い場合が有ります。 -
空調機吸込口のエアフィルタに目詰まりが発生している。
これも時々ある原因です。弊社の空調機は、故障が非常に少ないので、長い間には、メンテナンスフリーと勘違いされて、フィルタ清掃を何年も行っていない事が有ります。
吸込口のフィルタが目詰まりすると、空調機内の通過風量が低下して、所定の性能が得られなくなります。この症状は、フィルタを清掃すれば解決します。 -
空調機内部の冷却コイルが凍結している。
運転開始時に出ていた低温低湿の条件が、だんだん出なくなってきた場合は、冷却コイルの着霜が考えられます。着霜すると、最初に湿度が下らなくなり、放置すると、温度も下がらなくなって、次第に制御が不安定になってきます。
放置すると、冷媒が液の状態で冷凍機に戻り、液圧縮して、冷凍機の重故障になります。低温低湿度の運転では、冷媒の蒸発温度がマイナスの領域になりますから、冷却コイルには必ず着霜します。冷媒が少し漏洩して冷媒の低圧が下った場合も着霜し易くなります。
霜取を行わずに長時間運転すると、霜が凍結して完全な氷になり、霜取に時間がかかる様になります。霜がまだ少ない状態の時に霜取すれば、短時間で完了します。
また、着霜は、室内の風量を極端に下げたり、エアフィルタが目詰まりした状態で長時間運転すると発生し易くなります。
パッケージエアコンを利用した他社の装置では、送風機のVベルトが緩み、送風量が低下した事が原因で、恒温恒湿室でも、冷却コイルが凍結した例が有ります。冷蔵庫と同じ定時霜取方式では、扉を解放していた等の条件が有ると、極端に冷却コイルに着霜して、霜取時間中に霜が取り切れず、霜が次第に蓄積して凍結する事が有ります。連続の低温運転では、1度凍結した冷却コイルの氷は解けません。運転を停止しなければ、消える事は、まず有りません。
一般的な空調機では、吸込口から冷却コイルが見えますので、吸込口から懐中電灯で着霜、凍結状態を確認する事が出来ます。
弊社の環境試験室は、デュアルコイル方式ですから、運転を休止して霜取する必要は有りません。運転中に交互に霜取する方式で、低温でも完全な連続運転仕様です。
恒温恒湿室は、着霜する条件で運転しないので、霜取回路は有りません。環境試験室でも、他社の製品では、低温運転が出来ても、霜取回路が無い物を見受ける事が有ります。
この様な空調機の冷却コイルに着霜が発生した場合は、冷凍機のスイッチだけを切り、高めの温度に設定して運転すれば、循環空気の熱で除霜する事が出来ます。
但し、完全に透明な氷の状態になるまで凍結させてしまった場合は、これを解凍するのに、1日かかる例も有ります。 -
お部屋や扉に隙間が出来て、外気が侵入している。
10℃以下の温度で、10%以下の低湿度にする様な過酷な条件では、ケーブル孔や、わずかな扉のパッキンの隙間から侵入する湿気でも、夏季には大きな影響を受けます。
少しでも価格を下げる為に、ギリギリの設計をすると、この条件では、外気が少しでも侵入すると湿度が下がり難くなり、冷却コイルの着霜も激しくなります。
低温低湿でも換気を行いたい場合や、人の出入が多い場合は、冷凍機を1ランク大きくする必要が有ります。