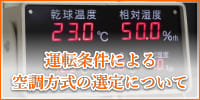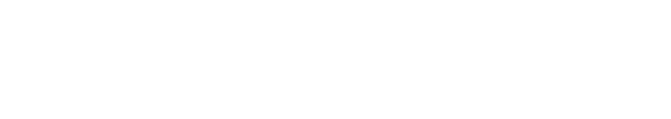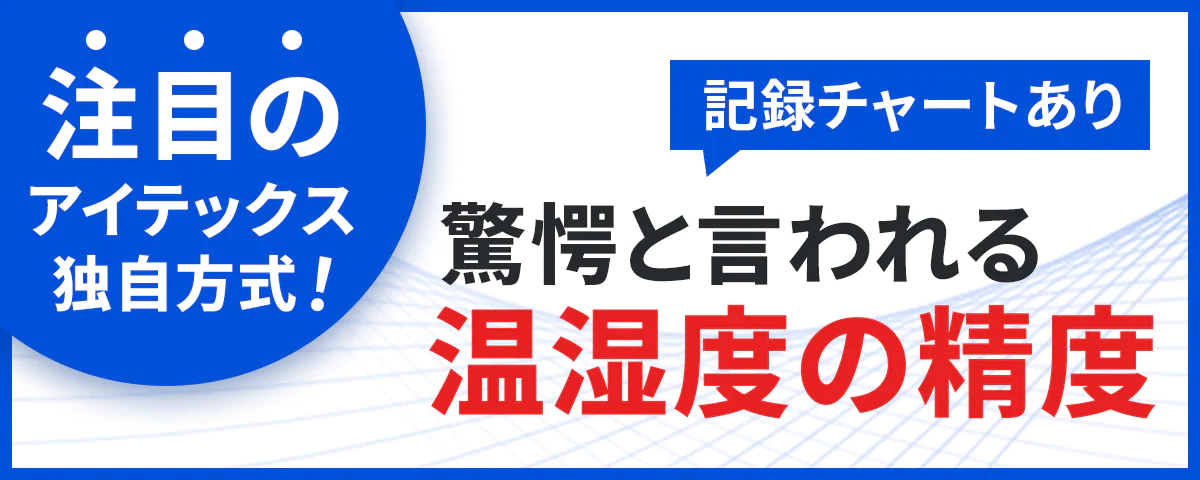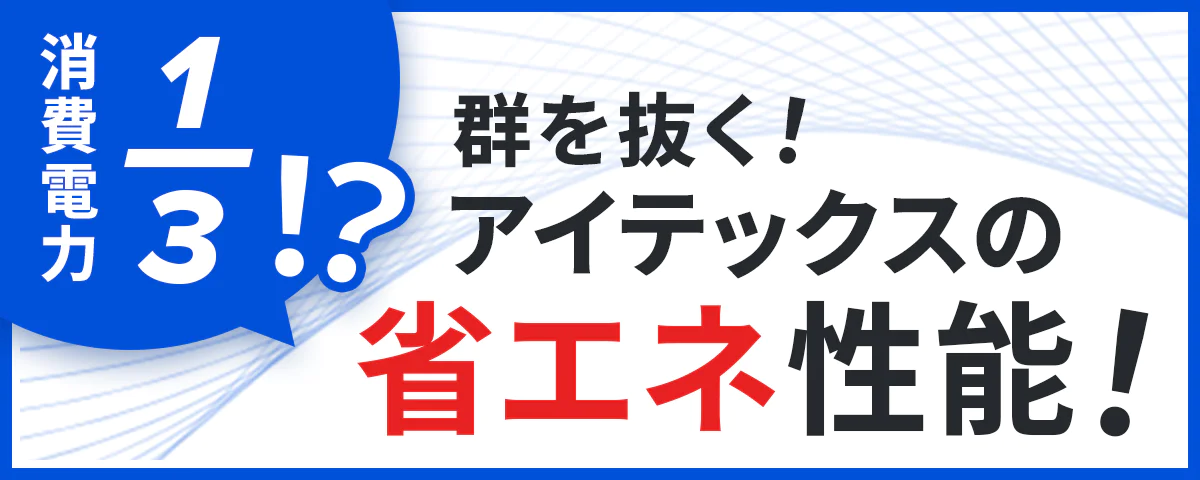精密空調の重要性について
簡単な制御方式は精密な測定には不向きです。
精密空調の重要性について
恒温室や恒温恒湿室の制御には、一般的な床置きのパッケージエアコンを利用して、これに加湿器を組み合わせた、良く有る簡易的なタイプと、専用の空気調和機を使用したタイプがあります。エアコン利用のタイプは、価格は安いのですが、消費電力が大きく、故障の発生率が高く、十数年程度で入れ替えている例が多く有ります。専用の空調機では、20年以上稼働している例が有ります。
温湿度の制御方法としては、大きく分けて、二位置方式、三位置方式と、現在主流のPID方式に分類されます。
簡単に言いますと、二位置方式は、乾燥庫や冷蔵庫等、温度を上げるだけか、下げるだけで、あまり精度を要求しない場合に採用される方式です。
三位置方式は室温が高ければ冷却して、低ければ加熱する方式です。設定温度付近は、中間帯と呼び、冷却も加熱しません。中間帯を広くすると、精度は落ちますが、省エネになり、狭くすると、精度は上がりますが、冷却と加熱を頻繁に繰り返して、省エネになりません。この方式は、以前は一部の恒温室等で使用されており、一番省エネな空調方式です。温度は、±1.5~2℃に保てますが、冷凍機のON-OFFにより、湿度が大幅に変動しますので、湿度の安定性を求める恒温恒湿室では、ほとんど使用されなくなりました。
PID方式は、発展の一時期に有った、比例制御や、PI制御が進化した物です。
現在も主流の制御方式で、恒温恒湿室屋環境試験室では、1番採用されている制御方式です。これは、エアコンの冷房や、冷凍機を連続で運転した状態で、加熱ヒーターを電気的に比例制御させ、安定な温度を得ようとするものです。
エアコンや、冷凍機の能力可変は技術的に難しいので、一般的には冷房の能力は固定しており、ヒーターを半導体電力調節器で微調整して、安定した温度を得ております。
現在の恒温恒湿室では、極めて高い精度が要求されますので、このPID制御が主流になっております。この方式は、夏季に合わせて冷却除湿量を選定して、十分に冷却、除湿してから、設定値まで加熱と加湿をする方法です。
エアコンや、冷凍機の能力は、夏季に合わせて選定しますから、冬季には、必要の無い軽客除湿をしてしまうので、ヒーターの稼働率が高くなります。
PID制御の冷凍機容量は、夏季の一番過酷な条件を想定して冷却除湿能力を決めますから、冬季には、どうしても能力が過剰になります。この為に、特に冬季はヒーターの消費電力が大きくなる欠点があります。
過剰に冷やしてから加熱すると、大幅に除湿されますから、冬季は大幅に加湿する必要が有り、さらに消費電力が大きくなり、加湿器の故障も多発します。
PID方式は、実は、エネルギー効率としては非常に悪い方式で、電気料金が高額で、加湿器の故障が多発する制御方式なのです。
エネルギー効率が悪いのにPID方式が主流なのは、三位置制御の様に冷凍機をON-OFFすると下記の問題が起こるからです。恒温恒湿室として、この様な簡単な三位置方式を採用すると、実際には、変動が大きくて、役に立ちません。
冷凍機のON-OFFが、室内温度と湿度に及ぼす影響
恒温恒湿室の温湿度センサは、通常は室内の壁面等に取り付けされております。実際には、この部分を20℃又は、23℃に制御している事になります。
三位置制御では、室温が高いと冷凍機が起動して冷却を開始しますが、センサには応答遅れがあります。特に室内の風の流れが悪いと、実際の空気の温度が設定よりはるかに低下した頃に、設定温度を検知して冷凍機を停止させます。
冷凍機に無理がかからない様に、ポンプダウン方式で停止させると、冷媒を回収する迄は冷却が続き、実際にはさらに冷却してから停止するのです。
エアコンの様に、直切りと言って、冷凍機の元電源で遮断する方法も有ります。この方法は、制御性は少し良くなりますが、起動の度に大電流が流れるので、冷凍機や、マグネットスイッチの寿命が短くなります。
温度調節計に表示される温度は、あくまでセンサ部分の検出温度です。加熱時も同様で、室内の空気温度がかなり上昇した頃に、壁面のセンサが設定温度に到達した事を検知して、ヒーターが停止します。
ヒーターはすぐに停止するのですが、室温がオーバーシュートしても冷凍機は直ちに起動しない場合が有ります。冷凍機を短時間でON-OFFするとモーターに大きな起動電流が流れ、これが繰り替えされると、過熱してしまうからです。
冷凍機保護の遅延回路が働き、一般的には3分程度遅延してから起動します。
センサの応答遅れが有る為に、温度調節計の指示はそれほど大きく変動しませんが、高感度の測定器で実際の室内温度を計測すると、調節計の指示は、±1.5℃程度なのに、実際の室内の温度は、±5℃も変動していた例もありました。
特にひどいのが湿度で、冷凍の運転で、冷却コイルの表面に凝縮して発生した水滴は、冷凍機が停止すると、直ぐに、自然蒸発式の加湿器に変化しますから、急激に室内湿度が上昇して来ます。
特に夏季に換気をしている場合等は、湿度の高い外気が入ってきても、除湿をしないので、室内の湿度は、さらに急激に大幅に上昇してしまい、室内の壁や床に、結露が発生してしまう事も有ります。
この様な方式で、温度 ±2℃、湿度 ±5%RH 等と表示している恒温恒湿室が有りますが、この性能は実は有り得ません。何故なら、23℃の室温が+2℃も変動したら、これだけの温度変化でも、湿度は±8%程度も変動するからです。
さらに冷凍機がON-OFFしたら、実際の湿度はもっと大幅に乱れます。
加湿器は沸騰しないと加湿しませんので、加湿命令が出て、実際に加湿が開始されるのは水か沸騰してからになります。この為、三位置制御では、湿度調節計の指示が±10~20%以上も大きく変動するのは当然なのです。
但し、これはあくまで、温度調節計と、湿度調節計の指示であり、検出の早い精密な測定器で測定すると、温湿度は驚くほど、もっと大幅に変動しています。
平均値でその温湿度が出ていれば良いとの考え方も有りますが、例えば、電話帳の様な、吸湿性が早くて、放湿性が悪い、厚い紙等の試験室では、湿度が大きく変動したら、この様な紙は吸湿したままになりますから、実際の状況とは測定結果が大幅に異なり、測定にはなりません。三位置の制御方式は、湿度が絡む精密な測定になると、実際には使い物にならないのです。
温度だけを見ましても、吹出口から吹き出す空気の温度は冷凍機が起動すると、急激に下降します。この冷たい空気が室内の被試験体に当たると、冷たい空気の当たる所だけが、真っ先に温度低下します。
センサには応答遅れが有りますから、温度調節計の指示が、設定温度に到達した頃には、風の良く当たる部分だけ、大きく温度が低下しています。
また、センサが設定温度を検知する頃は、検知が遅れ分だけ、実際には室内の温度はさらに低くなっています。
この為に、実際の室内温度の変動幅は、温度調節計に表示された温度よりも、かなり大幅に大きく変動しているのです。
冷たい風の当たらない部分は冷却されにくいので、同じ試験室の中でも複数のセンサで温度分布のデターを取ると、驚くほどのバラツキが発生します。
パッケージエアコンを利用した空調機の様に、1ヶ所だけの吹出では、長尺物の測定では、左右や、手前と奥では、大きな温度差が発生する場合も有ります。
この為、弊社では、室内にダクトを設けて、風を分散させて、風の分布と風量を微調整できる様に考慮して、低風速低騒音でも、温度分布を高めております。
床置きのパッケージエアコンと、加湿器を組み合わせた恒温恒湿室は、価格が安いので良く見るのですが、連続で冷却除湿して、ヒーターでバランスを取るPID方式は、精度は高くなりますが、ランニングコストが非常に高くなります。
また、加湿器の稼働率が高くなるので、加湿器のトラブルも多発します。
PID方式の恒温恒湿室を導入したら、電気料金が非常に高額になり、加湿器の故障も多発するので、これに驚いたお客様は、納入された後にメーカーに相談して、エアコンの冷房をON-OFFする様に改造した例も、良く見かけます。
ON-OFFに改造すれば、電気代は安くなりますが、これは前に説明した、三位置制御方式と同じになります。湿度が絡む精密な実験では、改造前と違う測定結果が出ます。精密な測定ができなくなくなったので、何とか消費電力を少なくしたままで、性能だけ上げられないかと言う相談が有ります。
この様な装置を、精度は高いままで、消費電力を1/3以下に改造した実績も有り、ホームページの省エネの項目で説明しております。こちらもご参照下さい。
精密な温湿度条件は欲しいが、PID方式では、高額な電気料金を支払う必要が有り、しかも多発する加湿器のトラブルで、高額な保守費もかかるのです。
これが、PID方式の恒温恒湿室や環境試験室を採用して、精度ではほぼ満足されても、皆様が一番悩まれている、電気料金の高さと、故障の多さなのです。
弊社では、長い間この消費電力の削減と、加湿器の故障多発問題に取り組んで来ました。この結果、加湿器を使用しないので故障が少なく、非常に精度の高いDPC方式と、加湿器を2台使用して、これを交互に洗浄して故障を防止するCSC方式を確立しました。
いずれの方式も、とても省エネで、故障の少ない空調方式です。
また、弊社のセンサには、特別に応答速度を高める工夫がされておりますから、どちらの方式も、極めて高精度な制御を行います。
弊社CSC方式は、冷却、加熱、除湿、加湿の4信号を比較演算して、冷凍機、ヒーター、加湿器は、必要最小の電力で制御する方法です。温湿度の移行時間が短く、安定性も高い方式で、各機器の稼働率が低くなりますから、消費電力の削減だけでなく、とても故障の少ない空調機になっております。
特に加湿器は、通常は1台使用する所を、同じ能力の加湿器を2台空調機に組込み込んでおり、通常の半分の電力にして働かせております。1台でも運転出来る能力が有りますから、加湿器が1台故障しても、湿度条件を乱さずに、警報だけ停止させれば、実験や測定は、そのまま継続して行う事が可能です。
また、弊社CSC方式は、加湿器の稼働率が低く、夏季は、加湿器を停止させ、除湿制御するだけで、安定した湿度を得ております。これは究極の省エネ運転になります。運転中の加湿器は交互に洗浄していますから、加湿器のトラブルは、他社製品よりも、かなり少なくなっております。
それでも、加湿器のトラブルは皆無では無いので、交換は、お客様でも簡単に行える様な構造にしておりますから、お客様自身で交換された例も有ります。
加湿器の在庫は常に確保しており、即日発送が可能です。特に遠方のお客様は、翌日に加湿器が到着して、ご自身で交換された例も有り、加湿器本体以外には、経費が掛からないので、とても喜ばれております。
ここで説明しているDPC方式と、CSC方式は、弊社独自の空調方式ですから、この名称で他社に問い合わせされても、何の事か判りません。
いずれの方式も、とても省エネで、故障が少なく、精度の高い方式ですから、ご興味の有る方は、弊社ホームページの恒温恒湿室の項目をご参照下さい。