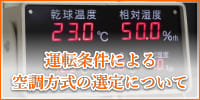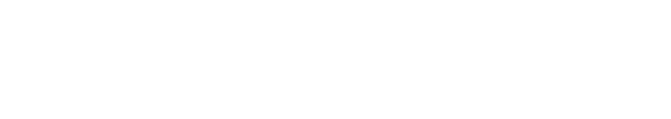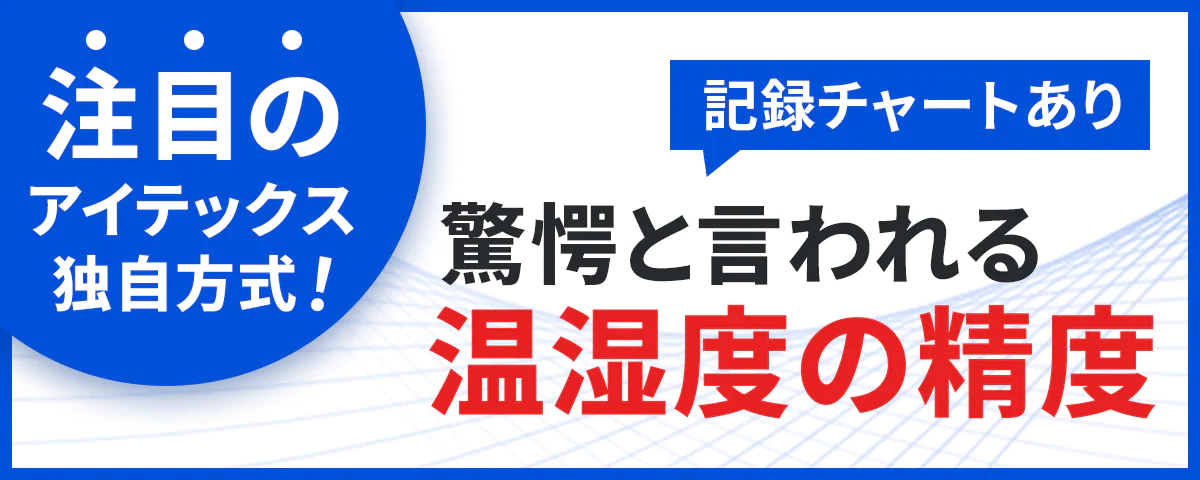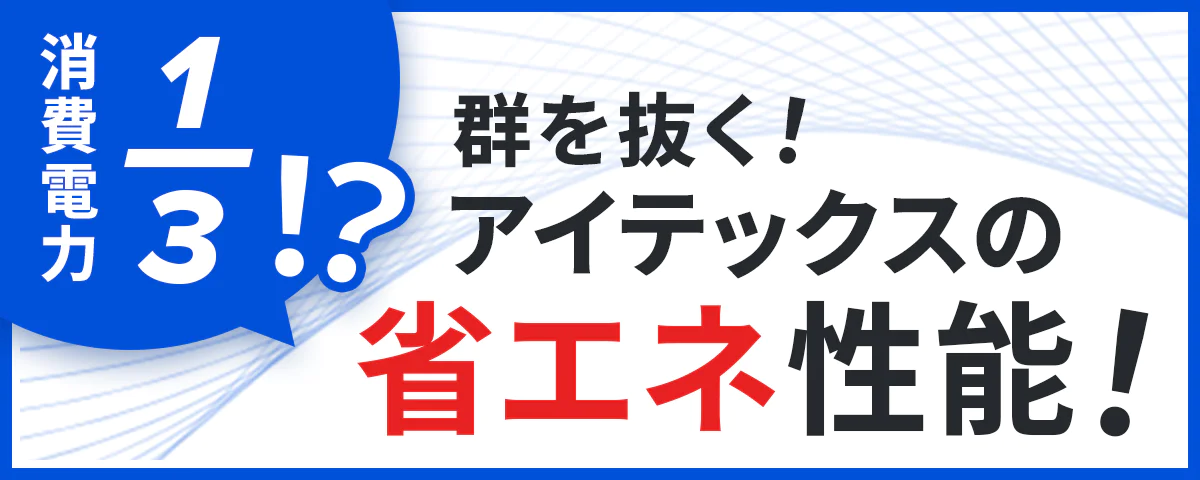湿球ガーゼを使用した試験室
湿球ガーゼ方式の温湿度センサについて解説します。
湿球ガーゼを使用した試験室
恒温恒湿室や環境試験室の温湿度制御を行うには、必ず正確な温湿度センサが必要です。
現在は、半導体湿度センサが主流で、湿球ガーゼで湿度を検出する方法は少なくなりましたが、古い装置の入替えでは、湿球ガーゼ方式も良く目にします。
乾球湿球方式による湿度の検出は、経年変化が無いので、精度的には非常に良い方法ですが、正確に測定するには、湿球ガーゼの管理が大変です。
時々温湿度の確認の為に使用されるアスマンの様な計器なら、湿球ガーゼは長持ちしますが、試験室の様に、毎日連続で使用すると、蒸留水を使用していても、ガーゼの表面に不純物が付着して、これが蓄積固形化すると、気化熱による湿球温度が下り難くなり、プラスの誤差を発生します。
この為、頻繁にガーゼを交換する必要が有りますが、純正のガーゼは高価ですから、これを使用しないで、適当なカーゼを適当に巻いている例を多く見ます。
一目で、これはまずいだろうと思われるのが、ガーゼの巻き過ぎです、ガーゼは一重が正しいのですが、数回巻いている例が多く、これですと十分に湿球温度が気化熱で低下しません。
湿球ガーゼの管理が悪いと、十分に湿球温度が下らず、湿度は高めに検出されます。
この方式では、湿度が実際より低く表示される事は、絶対に有りません。誤差は全て、実際の相対湿度より高くなります。
湿球ガーゼには、安定した一定の風速を当てる必要が有りますから、この方式のセンサは、空調機の吹出口に取付けして、吹出の風を当てている例が多いのですが、お部屋の中心温度と、吹出口の温度には、必ず差が有りますから、この位置で測定制御すると、お部屋の中心の温湿度とは差が出る事になります。
この様な事を考慮すると、正確に測定できる方法ではありますが、ガーゼの管理が非常に面倒で、実際にはプラスの誤差を発生している例が多く有ります。
この様な事情から、現在は半導体式の温湿度センサを使用する例が多くなっています。
半導体センサは、ドリフトする事は有りますが、定期的に別の正確な測定器と比較して管理すれば、乾きかけた湿球方式よりはるかに精度は高く、この様な手間はかかりません。
湿球ガーゼ方式のセンサをお使いの場合は、半導体式の温湿度センサに交換された方が、手間がかからないので、良いと思います。
弊社では、他社製品の、この様な改造も行っております。