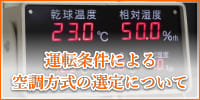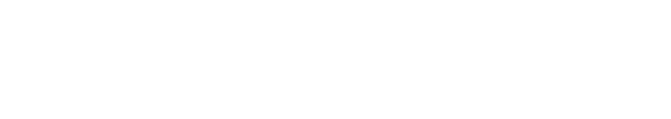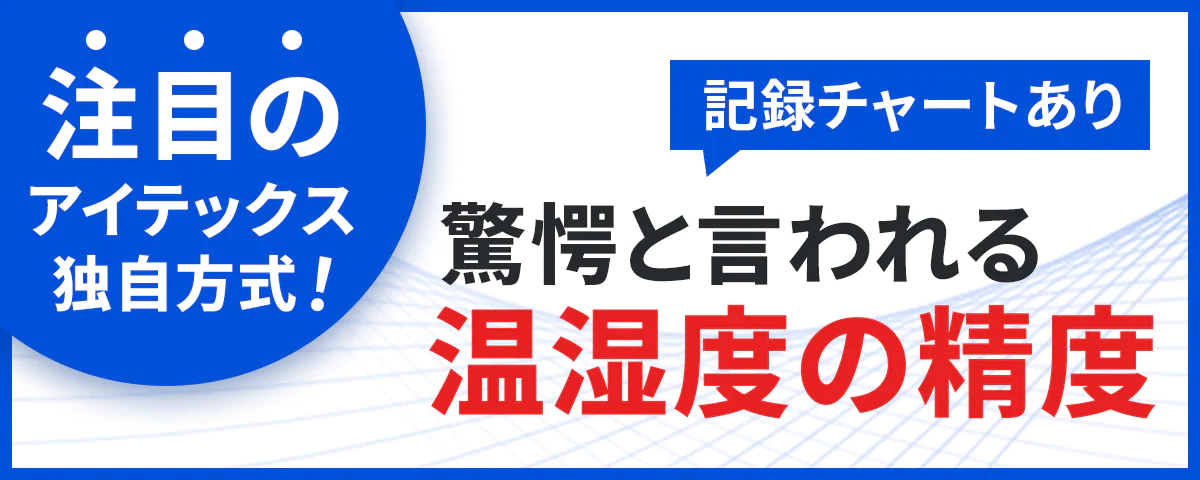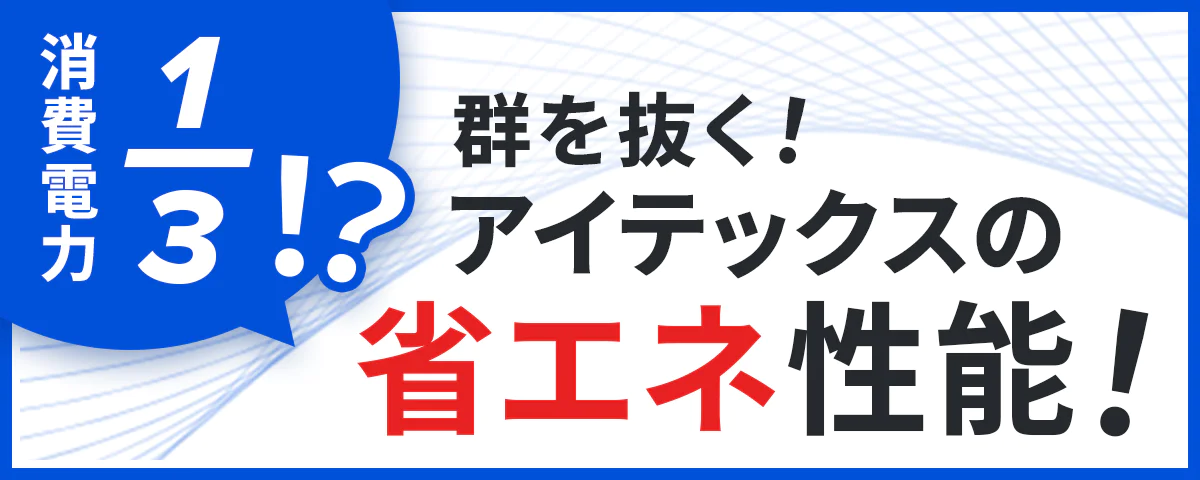PID方式と各種の空調方式
時代の流れで少しずつ進化する制御方式について解説します。
PID方式と各種の空調方式
一般的な恒温恒湿室や環境試験室では、加熱ヒーターと冷凍機、加湿器等を使用して、温湿度の制御を行っております。時代の流れで、制御方式も、少しずつ進化しております。
これらの温度、湿度の制御方法には、下記の様な方式が有ります。
二位置制御方式
これは一番古い空調方式ですが、現在でも、簡易型のエアコンや、高温室、乾燥機、冷凍庫、冷蔵庫などに使用される制御方式です。
家庭では、こたつや、ホットカーペット、電気毛布などに使用されております。
暖房や、高温室では、室内温度が下るとヒーターを入れ、冷蔵庫では、庫内温度が上がると、冷凍機を運転するON-OFFの制御方式です。
温度の安定性は、上がったり下がったりして低いのですが、乾燥機や、冷蔵庫の様に、平均してその温度付近をキープ出来れば良いと言う場合に採用される、一番簡単な方式です。
湿度は、変動する速度が非常に速いので、二位置制御で湿度を安定させる事は難しくて、±20%以上の変動が有ります。平均値で考え無いと、湿度の制御には使用できません。
この方式は、サーモスタット等、機械的な接点でON-OFF出来ますので、価格的には一番安く、必要以上に冷却、加熱しないので、1番省エネな制御方式です。
どんなに時代が進んでも、無くなる事は有りません。
三位置制御方式
二位置制御の様に、温度を上げたり、下げたりの一方的な制御では、室内温度を、設定された一定の温度に保つ恒温室は出来ません。
三位置制御では、設定温度より室内温度が下ったらヒーターで加熱して、設定値の直前で、ヒーターを遮断します。その後、設定より再び下降すれば、再度ヒーターで加熱して、設定付近に上昇すれば、ヒーターを遮断します。
室内温度の上昇が続いて、設定温度を超えれば、冷凍機を運転して冷却します。室内温度が低下して、設定値に近づくと、冷却を停止します。その後、再び室温が上昇すれば、冷凍機を運転して冷却し、室温が設定温度より低下すれば、またヒーターで加熱する事を繰返すのが、三位置制御と呼ばれる方式です。
設定値付近では、加熱も冷却も行わず、設定値から少しどちらかに室温がずれると、加熱か、冷却のどちらかを行います。
設定値付近の不感帯の事を中間帯(ニュートラルゾーン)と呼びます。
中間帯が狭いと、常に加熱か冷却のどちらかを行う様になり、省エネにはなりません。
また、中間体を広く取ると、温湿度の上下の制御幅が広くなりますが、省エネになります。
温度制御だけ必要な恒温室に使用される例が多く、広いお部屋ですと、±1℃程度の精度が得られますが、小さなお部屋では、移行時間が早いので、制御幅が広くなります。
また、室内の湿度は、冷房がON-OFFするので、大幅に変動してしまいます。
湿度の制御も可能ですが、湿度は移行が早いので、冷凍機の運転で室内の湿度は大きく変動しますし、加湿が必要になっても、お湯が沸騰する迄は加湿しません。加湿器が立ち上がると、急激に加湿するので、ここでは毎回大きなオーバーシュートが発生します。
温度が安定できても、湿度は大きく暴れるので、湿度の影響を受けやすい紙や繊維等の実験では、測定結果に大きな支障が出る場合が有ります。
現在では、この様な事情がありますから、三位置制御方式は、簡易な装置以外には、ほとんど使用されておりません。
PID制御方式
PID制御も古い制御方式ですが、他に良い方法が無いので、現在でも主流の制御方式です。比例(Proportional) 積分(Integral) 積分(Derivative)の頭文字を取って、PID方式と呼んでいます。
過去の一時期には比例制御だけや、PI制御等も有りましたが、現在はほとんどの空調方式が、PID制御になっています。
PIDのそれぞれの機能は、概ね下記の様な働きをしています。
P 調節出力を設定値に近づける働き
I 出力値を設定値に留める働き
D 出力値の変動を防止して、安定させる働き
何だかよく解らないと思いますが、現在は、調節計にオートチューニングの機構が付いておりますので、比較的容易に良い制御結果が得られる様になりました。
PID制御は、非常に安定性の高い制御ですから、従来から、一般的な試験室の空調には良く利用されて来ましたが、下記の様な欠点も有ります。
冷凍機を定格電力で運転したままで、加熱ヒーターを精密制御して温度を安定化させています。言い方を変えると、冷却と加熱を喧嘩させる方式なので、消費電力が大きくなります。
特に冬季は、冷やし過ぎた分を補償するので、消費電力が大きくなります。
また、冷却してから再加熱すると、除湿します。夏季は外気湿度が高いのですが、除湿してしまいますので、湿度の高い夏季でも、加湿器で加湿して設定湿度を得ています。
空気の乾燥する冬季でも、温度を制御するためには、冷凍機の定格容量の冷却をしてから、必要なだけの加熱をしますから、湿度の低い冬季には必要の無い除湿を行います。
この為、室内の湿度は、大幅に低下してしまいますから、加湿器の稼働率は、必然的に高くなります。加湿器の無い恒温室では、極端に室内の湿度が低下します。
この為、PID方式は、冬季は、加熱と大量の加湿が必要になり、特に冬季の消費電力が大きくなります。加湿器の稼働率が高いと言う事は、加湿器の故障も多発します。
また、温湿度の設定を高く設定変更すると、大きなオーバーシュートが発生して、安定する迄には、時間がかかります。
この様な欠点が有るのですが、PID方式は、現在でも、業界では主流の空調方式です。
弊社で改良した空調の方式
PID制御方式には、この様な欠点が有りますから、弊社では制御方式を工夫して、実験する目的に合わせて、下記の2機種の空調方式の空調機を開発しております。
DPC方式
冷水を直接使用して冷却除湿と、自然加湿を行う方式です。非常に安定度の高い方式です。消費電力が少なく、夏季には、加湿する水道水すら消費しません。故障がとても少ないので、非常に運転経費が少ない空調方式です。
他社にも、露点散水方式と呼ばれる類似の方式が有りますが、その精度、省エネ性、故障率は大きく異なりますので、弊社では、あえてDPC方式と呼んでおります。
この方式の詳細は、別途ホームページのDPC方式のページで公開しております。
ご興味の有る方は、こちらをご参照下さい。
CSC方式
DPC方式は、冷水で温湿度の制御を行いますので、低温低湿では、冷却水が凍結します。
幅広い温湿度を要求される環境試験室の場合は、CSC方式で対応しております。
これは、一般的な加湿器を使用するPID方式を、独自に改良した物で、問題であった加湿器の故障が大幅に少なくなり、消費電力が従来の1/3以下になる等の特徴がある、とても省エネな空調機です。
この詳細は、別途ホームページのCSC方式のページで公開しております。
幅広い運転範囲をご希望の場合は、こちらをご参照下さい。
この外、さらに過酷な条件で使用するDCS (デュアルコイル)方式や、霜取休止しないで、低温低湿度を連続で得る方式、除湿制御と湿度監視の出来る恒温室等、お客様が希望される運転条件に合わせて、各種の装置を設計製作しております。
他社の試験室を、弊社の空調方式に交換して、極端な性能向上と、省エネに改造した実績の資料もホームページで公開しております。
良く有る宣伝用の文章では無く、改造の実績集ですから、ぜひ、こちらもご参照下さい。