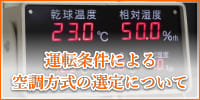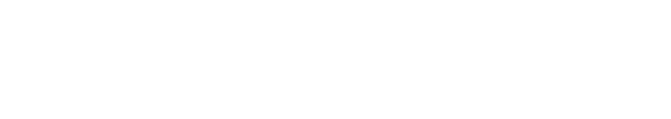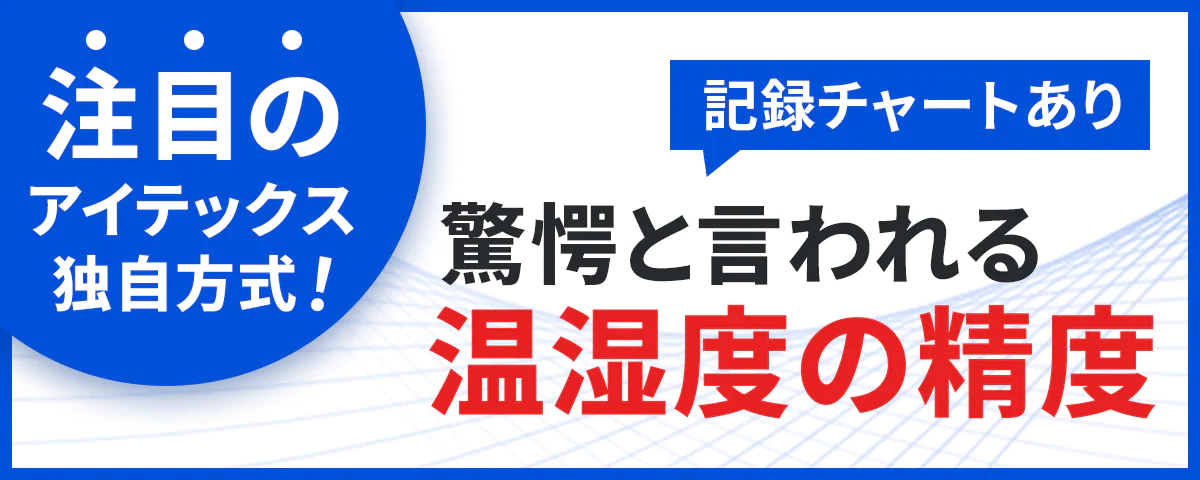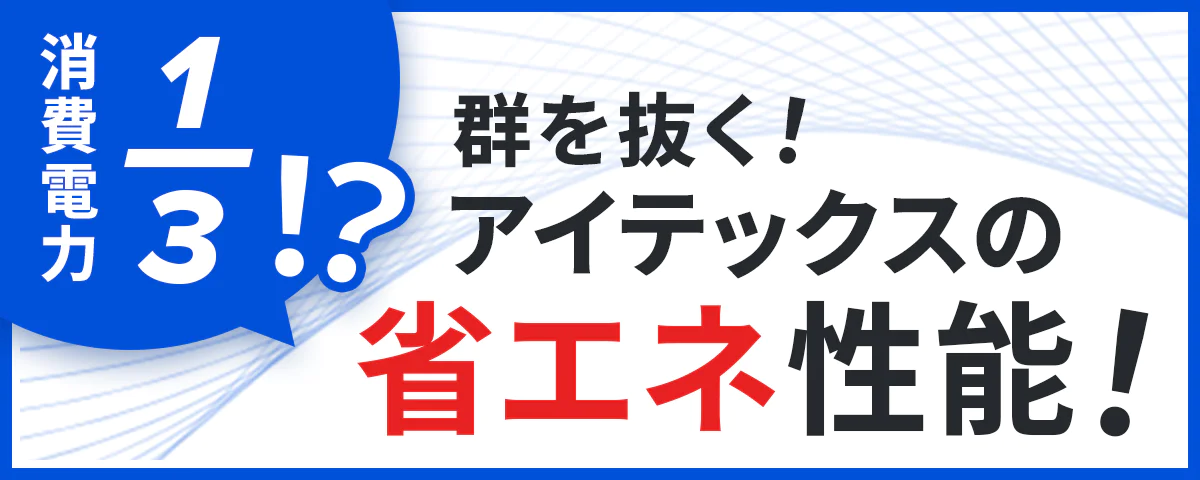ノイズ対策
付近の精密機器のためにも、ノイズ対策は必要です。
試験室のノイズ対策
恒温恒湿室や環境試験室で、どうしても温湿度が安定しない事が有ります。
室内の温湿度が、実際に移行するのには時間がかかりますので、温度調節計や湿度調節計の指示が、パラパラと不規則に変動したり、突然指示値が飛ぶ場合は、ノイズの影響を受けていると考えられます。
ノイズ発生は電子機器からが多く、現在は電磁波の影響を避けるEMC対策が進み、ノイズ発生側、ノイズの影響を受ける側の対策が進み、かなり少なくはなりましたが、現在でも、ノイズの影響により、温湿度が乱れる現象は、時折発生しております。
ノイズとは、幅広い周波数帯域を持つ電磁波の雑音ですが、電源機器から発生する高調波のラインノイズと、電子部品から発生する高周波の放射(輻射)ノイズが有ります。
厄介なのは、放射ノイズで、電波と呼ばれる領域のノイズですから、電線が直接接続されていない離れた場所の機器にもノイズが混入して、温湿度に影響を及ぼす事が有ります。
小さな部品なのに、大きな高周波のノイズを発生する物が有ったりしますが、伝搬ルートが見えないので、ノイズ発生原因の発見が非常に難しいノイズです。
温度センサは、白金測温体 Pt100Ω が使用されている事が多く、白金は非常に安定した物質ですし、温度による抵抗の変化も直線的ですから、これは非常に使い易いセンサです。
専門的には、インピーダンスが低いと言いますが、外部からのノイズには非常に強く、配線距離も、かなり長く伸ばす事が出来ます。
また、温度センサがノイズの影響を受ける事は、過去にあまり例が有りません。
温度側がノイズの影響を受けている場合は、かなり大きな原因が有りますから、比較的簡単に原因がわかり、ノイズ対策が出来ています。
湿度センサは、現在半導体式が主流ですが、この信号はとても微弱です。これを増幅して湿度調節計に、現在湿度を表示させておりますので、湿度側は、どうしてもノイズには弱いと言えます。
また、湿度センサの検出速度は、温度センサと比較するとかなり速いので、加湿器の制御性等に何か問題が有ると、湿度は変動しやすくなります。加湿器によっては、湿度をピタリと安定させるのが、とても難しい作業になる事が有ります。
湿度は、検出するセンサの信号が微弱ですから、外部からのノイズの影響を受けやすく、温度は極めて安定だが、湿度が安定しないと言う現場は、良く有ります。
湿度の安定性が悪いので、何回も湿度調節計のオートチューニングを行ってみたが、どうしても湿度が安定しないと言った場合は、加湿器本体に問題が有るか、湿度センサがノイズの影響を受けている可能性が有ります。
湿度が周期的に上がったり下がったり、設定値を中心に、ゆっくりと数%変動するのは、ハンチングと呼ばれる現象で、これは湿度調節計等の制御性に問題が有ります。
湿度の指示がパラパラと早く乱れたり、数秒で数%以上変化するのは、何らかのノイズが、湿度センサの回路に影響している状態と考えられます。
湿度センサの検出がいくら早いとは言え、実際の室内の湿度がパラパラと変化する事は絶対に有りませんし、扉を開閉しなければ、急激に数%以上変化する事も有りません。
センサに息でも吹きかけない限り、室内で湿度を測定しているセンサは、数秒間では、それほど早く、大きくは変動しません。湿度が早く大幅に変動する場合は、ノイズの影響です。
ノイズで、温湿度が不安定になっている場合は、まず、ノイズが外部から来るのか、空調機や、制御盤の中で発生しているのか、最初に判断する必要が有ります。
休日に、工場の機械類を全て停止させると、温湿度が安定する場合は、間違いなく外部から、何等かのノイズの影響を受けています。
1台ずつ機械を運転するか、1台ずつ停止させて、ノイズを発生している機器を探します。ノイズの発生源が判れば、発生源で対策するのが早道です。
ノイズを受ける側で対策するのは、どんなノイズが、何処から飛び込んで来るのかは、全く判らず、複数の総合的なノイズも有るので、解決するのは、意外に大変な作業になります。
臭い匂いは、元から絶たないと駄目と言う諺が有りますが、ノイズも元から絶っておかないと、周囲に有る、他の精密な機器にも、いずれ影響する事になります。
近年の制御盤は、内部の部品に半導体を使用した部品が多用されております。近年は少なくなりましたが、使用した部品の中の半導体が、ノイズを発生している場合も有ります。
特に送風機に使用しているインバータは、交流を直流に変換した後に、この直流をパルスにして、疑似的な交流を作っています。取り扱う電力が大きく、パルスの波形には多くの高調波が含まれる為、一番ノイズの発生源になりやすい部品です。
過去には、試験室を運転すると、試験室の付近に有る精密な測定器にインバータのノイズが影響して、測定誤差を生じた等の事例も有ります。
この様な経験から、弊社の制御盤はインバータのノイズをできるだけ防止する為に、標準で、ラインフィルタ、ラジオノイズリアクトル、DCリアクトル等を取付けして、自身の温湿度の制御の安定性だけでなく、外部に及ぼすノイズの影響等も、極力防止しております。
インバータと、送風機の間の配線が長いと、この配線から電波領域の電磁波ノイズが飛び出す事が有ります。この場合は、インバータの出口側にも、フィルタが必要です。
これらの部品は高額ですから、全部見積に乗せると金額が上がります。山の中のゴルフ場の人工滝に使用するが、周りには何も無いから、そんなものはいらないと言われて、ノイズの対策をまったくしないで、人工滝の制御盤を納品した事が有りますが、その後、このゴルフ場の付近に行くと、ラジオに雑音が入り、全く放送が聞こえなくなると言う話を聞きました。

左側はインバータ本体、右側はノイズ対策部品の例
この様に、制御盤の内では、送風機のインバータが1番のノイズ発生源になります。温湿度が不安定な場合は、送風機のインバータを停止させて、温湿度関係の計器だけ動かし、指示が安定するかどうか調べます。指示か安定すれば、インバータから発生したノイズの影響だと考えられます。
この外、電子式の計器類は、内部にスイッチング電源と呼ばれる直流電源を使用している例が多く、製品によっては、このノイズが大きく、これが原因になっていた事も有ります。
また、弊社では、インバータ冷凍機を使用しておりますが、この内部にも、当然インバータがあります。冷凍機の内部でもノイズ対策をしており、冷凍機は制御盤から離れた屋外に設置しておりますが、ここから電線を通して、冷凍機のノイズが影響する事も有ります。
この場合は、冷凍機を停止させて、湿度のふらつきが止まれば、冷凍機がノイズの原因と言えます。但し、冷凍機を停止すると、室内の温湿度は自然に上昇してきますので、自然な上昇なのか、ふらつきなのか判りません。
冷凍機を止めたまま、しばらく運転して、湿度の上昇がほぼ止まってから、湿度がふらついてないかを確認します。
200Vの電源のアース線は、変電室迄、長々と空中を配線されて来ている例が有ります。
これはアンテナを張ったのと同じ事になりますから、近くに放送局等の、強い電波が有ったり、強いノイズを発生する装置が有りますと、アース線を通して、電波による影響を受ける事があります。
また、アースは1点アースが基本とされておりますから、アースは各機器からのアース線を全部1ヶ所に集めて、1ヶ所でアースします。
アース線が途中で分岐されていたり、渡りを取ると言いますが、ある機器のアース端子から、他の機器のアース端子へ、同じアースで同電位だから問題無いだろうと、アース線を繋ぐと、これは多点アースと同じ事になり、ノイズの元になる事が有ります。
制御盤のアース線を端子台から外したり、センサのシールド線のアースを外すと、症状が和らぐ場合は、アース線から電波のノイズを拾っている可能性が有ります。制御盤のアースだけを、建物の鉄の構造材や、金属の水道管に接続すると解決する場合が有ります。
建物にノイズが乗っていた例も有りますから、地面にアース棒を打ち込んで、制御盤のアースだけ、他のアースと切り離して、単独アースにすると、良いノイズ対策になります。
パソコンなどの電源ケーブルの根元を見ますと、フェライトコアと呼ばれるノイズ対策用の小さな黒い部品が取付けられている事が有ります。

フェライトコアは左の写真の様な物で、ネットでも購入する事が出来ます。
下の方の写真の様に、ヒンジとフックが付いており、電線の上から、パチンとはめるだけの構造ですから、価格も安く、後からでも簡単にノイズ対策が出来ます。
1つで効果が無い時は、2個、3個と取付て、ある数で、急に効果が出る事も有ります。
長い間、空調と、計装に携わって来ましたが、ノイズは目に見えず、空間を飛びますから、何が原因なのか、なかなか判りません。ノイズ対策は、最も難しい仕事で有ると思います。