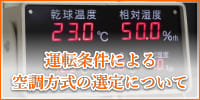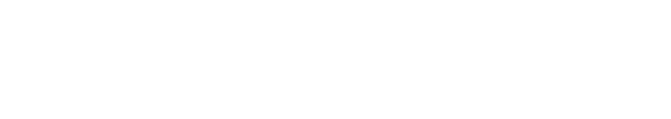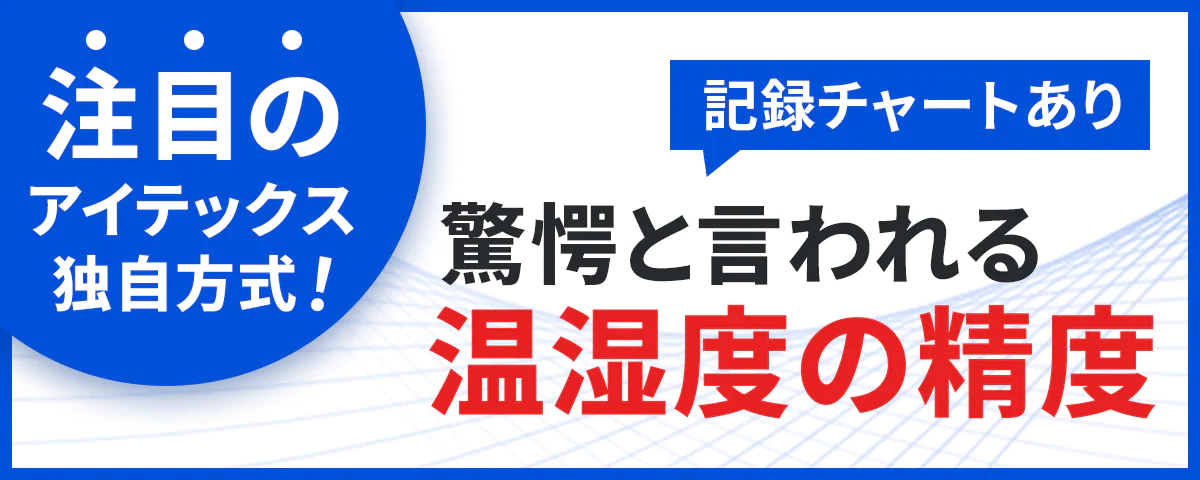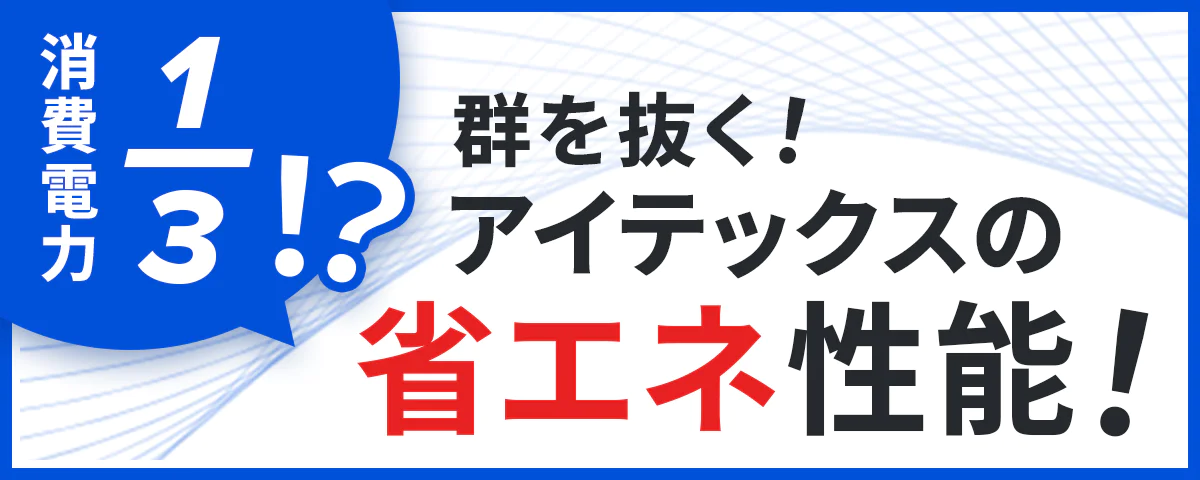運転停止に伴う湿度の上昇
精密な試験には安定した湿度が不可欠です。
運転停止に伴う湿度の上昇
恒温恒湿室や環境試験室の運転を停止すると、一般的に室内の相対湿度は高くなります。
この試験室の中に、電話帳が有ったとします。運転を停止すると、室内の湿度が上昇して、電話帳等は直ぐに吸湿して、ページをめくると、フニャフニャになっているのが判ります。運転を再開して、室内の湿度が低下しても、電話帳の中は、なかなか乾きません。
これは、吸湿性が良く、放湿性が悪いからです。
3.11東日本大震災の時には、原発の停止に寄り、関東地区では、1日に4時間の停電が計画されて、恒温恒湿室が、4時間だけ停止しました。この停止中に室内の湿度が大幅に上昇してしまい、試験中のサンプルが吸湿して、全く測定にならなかったと聞いております。
また、これ以後、電気料金が高騰した為に、消費電力の大きな恒温恒湿室は、夜間と休日は停止する様に、経営者側から指示が出され、これ以降、湿度がからむ精密な試験が出来なくなったと、大変困っている研究者の声も、良くお聞きしました。
試験室を停止すると室内の湿度が上がる理由
夏季に恒温恒湿室で、20℃/65%~23℃/50%の運転をしていたと仮定します。
運転停止時には、冷却と加熱ヒーターを停止させて、ヒーター部分の予熱を放出する為に、送風機だけ数分間残留運転させてから、停止せるのが一般的です。
冷却が停止すると、冷却除湿して、濡れている冷却コイルから、この水が蒸発します。冷却コイルは、自動車のラジエーターの様な形状ですら、これは、表面積が多く、とても効率の良い加湿器になります。運転を停止すると、アッと言う間に、相対湿度が上昇します。
換気していた場合には、夏季の高温多湿の空気が、室内に入ります。室内は20~23℃に冷却されているので、冷たい壁に触れると、ここに結露が発生して、壁面が濡れて来ます。
たとえば、夏季の30℃/70%の空気の露点温度は、24℃です。夏季に、30℃/70%以上の空気が入り込めば、23℃のお部屋の壁は必ず濡れて来ます。
30℃/60%の空気の露点温度は、21.4℃ですが、20℃のお部屋では、この位の外気条件でも、外気が入り込めば、壁が結露して濡れて来ます。
扉を閉めたまま停止すると、次に運転を開始する迄、室内は濡れて多湿になった状態のまま、ずっと保持される事になります。
冬季に停止した場合は、室温が次第に低下して来ますから、相対湿度は上昇してきます。
23℃/50%のお部屋の露点温度は、12℃ですから、壁が12℃まで冷えれば、これだけで、室内の相対湿度は100%になります。これ以下に壁が冷え込めば、壁面に結露します。
結露迄は発生しなくても、恒温恒湿室は、運転を停止すれば、この様に室内が多湿になる事は、ご理解いただけると思います。
試験室の運転を停止させる場合は、出来るだけ扉を解放して、室内の湿度を下げる事は、中のサンプルの為だけでは無く、試験室を長持ちさせる秘策にもなります。
湿度が変化すると性質が大きく異なる、紙製品等の試験室は、年間連続で運転されている例がほとんどです。年間の運転経費の安い機種を選定しないと、1年間では、数百万円と言う、とんでもなく大きな金額になります。
販売価格の安い空調機
恒温恒湿室は、20~25℃/50~70%程度の条件で運転される例が多く、これはエアコンの冷房運転と同じ温度域ですから、汎用の事務所冷房用のパッケージエアコンを利用して、恒温恒湿室を製作している例が多く有ります。
冷房専用のパッケージエアコンに暖房用のヒーターを組み込み、加湿器を取付けて、電気的に制御すれば、簡単に恒温恒湿室が作れます。パッケージエアコンは汎用品ですから、仕切り価格は安く、この方法が1番安く恒温恒湿室が作れます。
技術的にも簡単ですから、参入する業者も多く、最終的には、価格競争になっています。
パッケージエアコンの定価を見せられて、恒温恒湿室の見積書を見ますと、凄く得をしたような気分になりますが、この方式は、実は業者の利益率も高いのです。
この方式は、PID方式と呼ばれていますが、消費電力が大きく、加湿器の故障が多発するので、年間の経費が高額になります。但し、見積価格が安いので、実情が判らないまま、この様な業者に発注される例が多く有るのです。
購買の担当者は、要求した温湿度条件が出るのなら、安い物を購入するのが私の役目で、電気料金は、私が支払うのでは無いから、関係無いと、極論を言われるお客様もおられます。
パッケージエアコンを利用した場合の問題点は、技術資料のパッケージエアコン方式で、詳細に説明をしておますので、こちらをご参照下さい。
また、PID方式で多発する加湿器の故障は、技術資料の加湿器のトラブルと純水器で、詳細な説明をしておりますので、こちらもご参照下さい。
パッケージエアコンには、3.75kW(5馬力)以下の小型の機種が無くなりました。この様な方式を採用している業者は、小さな恒温恒湿室でも、やむなく、5馬力のエアコンを使用しています。エアコンの価格は大きく変わらなので、購入する価格は大きく変わりませんが、小さなお部屋なのに、消費電力が極端に大きくなります。
これも、高額な電気料金は設置した業者が支払う訳では無いので、売れさえすれば良く、購入時に、この装置は、他社より電気料金が高くなりますとは、口が裂けても言いません。
購入してから、高額な電気料金と、多発する故障に悩まされる事になります。
安定した湿度で連続運転するには
年間を安定した湿度を保つ為に、恒温恒湿室は、年間を連続運転している例が多く有ります。この為、消費電力の大きな装置では、高額な電気料金がかかります。
消費電力の大きな、パッケージエアコンを利用した恒温恒湿室を連続運転すると、電気料金が高額になるだけでなく、多発する加湿器の故障に悩まされる事になります。
高額な運転経費に、かなり悩まれてから、空調機だけを、省エネで故障の少ない装置に入れ替えたり、改造する例が良く有ります。 弊社ホームページの省エネの項目で、この省エネ改造の実例を乗せておりますので、ご参照下さい。
これらの実例は、他社の装置を、弊社独自のDPC方式に入れ替えた物や、既存の装置を、弊社のCSC方式に改造した物です。消費電力は、悪くて1/3、改造前の装置が過剰設計の場合は、1/6以下になった実例も有り、故障も極端に少なくなります。削減された電気料金は、軽く数百万円になりますから、この改造費は、数年で回収が出来ています。
CSC方式には、標準で省エネモードが有り、省エネモードでは、精度はJIS2級程度に低下しますが、消費電力は、1/10以下に低下した実例も有ります。
どのお客様も、こんなに節約になるなら、もっと早く実行するべきであったと言われます。
DPC方式、CSC方式の詳細は、弊社ホームページの恒温恒湿室の項目をご参照下さい。
他社に問い合わせされても、これは弊社独自の方式ですから、何の事か判りません。