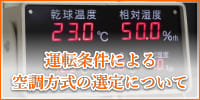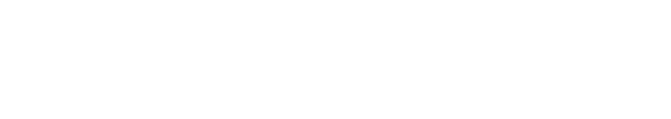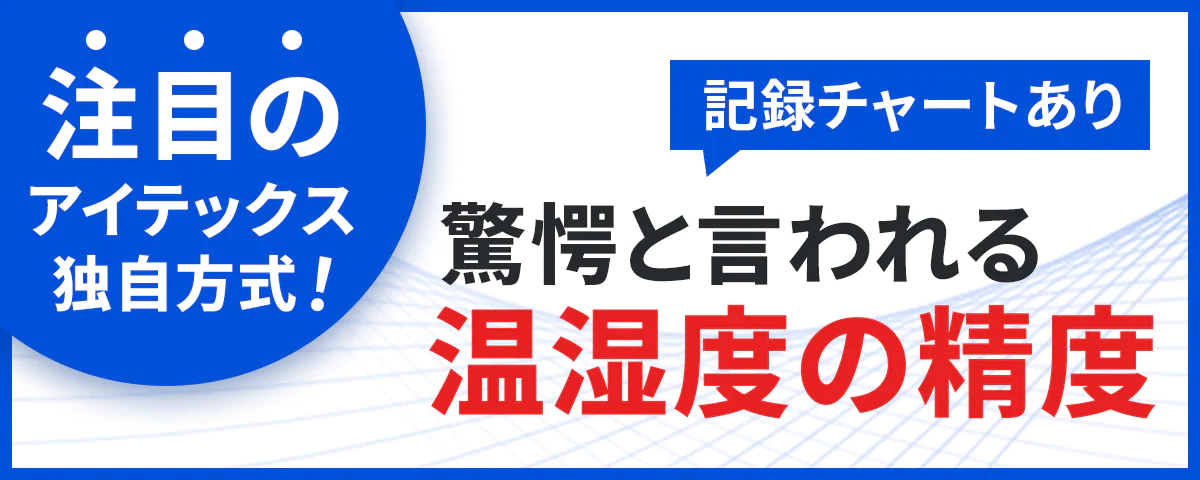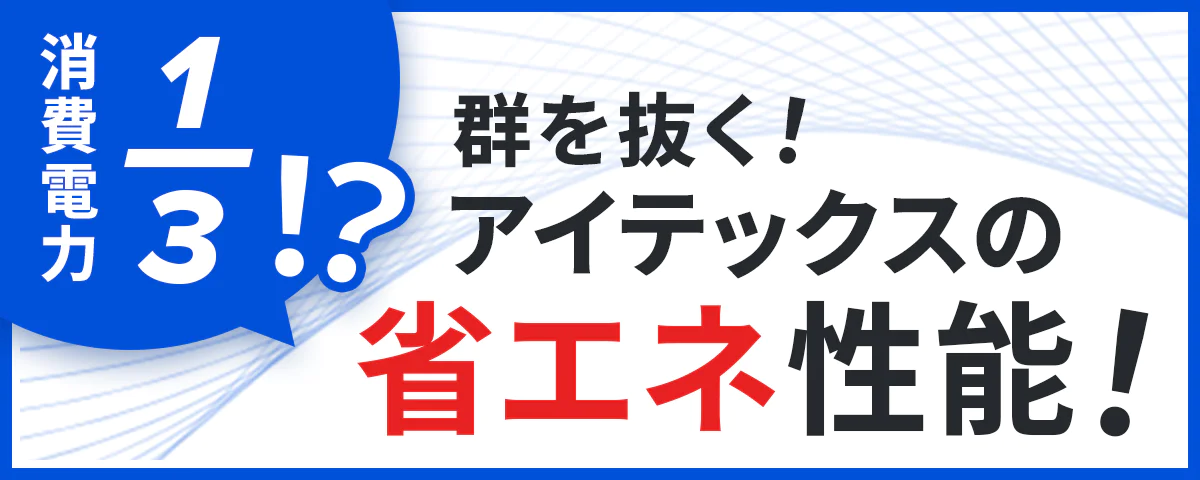熱負荷の考え方
発熱量の正しい見積は、適切な運転経費に繋がります。
熱負荷の考え方
空調設備を業者に相談すると、必ず、室内に発熱する物が有るか無いかを聞かれます。
また、換気量をどの程度考えるかで、冷却する為の能力が大きく変わります。
夏季や冬季に、必要以上に給気量 (換気量) を見ると、これも大きな熱負荷になります。
室内の発熱が大きいと、実際に必要な冷却量は、その分だけ増えますので、エアコンや、冷凍機の能力が大きくなります。この空調機を運転中に、もし、室内の発熱が想定したより少ないと、その発熱の少ない分は、ヒーターで加熱して、設定温度でバランスさせますので、消費電力が大きくなります。
特に、低温運転を行う試験室で、発熱や、夏季の換気量を大きく見過ぎると、設備費が高額になり、一般的な空調方式では、冷却量が大きくなるので、消費電力も大きくなります。
本当に室内の発熱が多い場合は、空調機の冷却能力が大きくなるのは当然ですが、発熱量をあまり多く見過ぎると、大きく見た分だけ冷凍機の能力が大きくなり、温度が低下するので、温度を設定に保持する為の加熱ヒーターが大きく働き、消費電力が大きくなるのです。
冷却し過ぎて、再加熱すると、大幅に除湿する事になります。すると加湿器の稼働率も高くなります。特に冬季になると消費電力が増大して、加湿器の故障が多発する事になります。
実際に発熱する量を正確に把握して伝えないと、空調装置の能力が必要以上に大きくなり、年間の運転経費が非常に高額になってしまうのです。実際の現場を見ますと、過剰設計された装置が、実に多く見られます。これは、下記の様な事が原因になっています。
大手の企業では、営業と、技術は別で、営業の聞いてきた話から、技術が設計を行います。
室内の発熱量を聞くのは、営業専門の担当者で、技術的に詳しくない方も多くおられます。
そこで営業担当は、お客様の言われる発熱量を、そのまま熱負荷として技術に伝えます。
お客様も専門の分野ではプロですが、電気には詳しくない場合が有ります。そこで発熱量を問われると、室内に入れる予定の機器の定格電力を全部加算して、営業に伝えます。技術は実際の状況を知らないので、そのまま熱計算してしまい、とんでも無く過大な能力の空調機が納入されてしまっている例が、実に多いのです。
また、設計では、安全率として、1.1~1.2程度は、能力を多めに見ますから、さらに実際に納入される空調機の能力が大きくなってしまいます。
実際に装置を納入してから、希望する温湿度条件が出なかったら、大問題になりますから、特殊な条件や、自信のない技術者は、さらに空調機の余裕を大きめに見る傾向も有ります。
パッケージエアコンを利用する方式では、3.75kW以下の機種が有りませんから、小さなお部屋で熱負荷が無くても、3.75kWを採用しますから、これはかなりの過剰設備になります。
エアコンは汎用品ですから、空調機の見積は安くなりますが、電気料金は高額になります。
装置の価格が安いので、この様な機種を選定しがちですが、電気料金の支払いはお客様です。設計者は電気料金が高くても、全く関係が無いので、この様な過剰設計が起きるのです。
弊社では、お部屋の広さと熱負荷に合わせて、冷凍機を、0.75kW、1.1kW、2.2kW等と、細かく選定しておりますから、過剰設備にはなりません。
また、冷却除湿の能力は、必要に応じた自動可変方式ですから、とても省エネになります。
たとえば、電気炉等は、実際に最大電力で働くのは、温度が上昇するまでの間で、設定温度に到達すれば、保持するだけの小さな電力になります。ヒーターの消費電力と発熱量は同じですが、本体は火傷をしない様に保温されていますから、外側はたいして熱くなりません。
定格電力×台数で考えると、熱負荷が大きくなり過ぎるのです。
また、引張試験機や、圧縮試験機等では、大きなモーターか取付けされている場合が有りますが、これも、実際にモーターが動くのは、圧力をかけている間の数10秒です。
定格電力が大きくても、実際に動く時間が短く、1時間当たりで計算すると、発熱する量は、非常に少ない事が有ります。
ある現場で、三相の30Aコンセントに太い電線で繋がれている試験装置が有り、カタログの電源容量は、3相の30Aが必要と記載されておりました。計算上の消費電力は10kWにもなるので、これを小さな試験室の中に入れると、空調機だけがかなり大きくなります。
そこで、その試験機のメーカーに問い合わせしましたら、30Aが必要なのは、最初の数秒だけで、後はほとんど電力を使用しないとの話でした。
お客様の言う、電源の定格を信じて、そのまま設計したら、極端な過剰設計になる所でした。これでは、設備費は高額になるし、試験機が停止していても、空調機は大きな電力で運転しますから、そのままで設計したら、必要の無い高額な電気料金を支払う事になる所でした。
また、お客様が室内に入れる予定の機器の定格電力の一覧表を作成して、これだけの電力が必要だと言われる事は、実際に良く有ります。
単純に定格電力を全部足し算して、その値を熱負荷として言われる事は良く有るのです。
この様に計算された熱負荷の表を信じて設計したのではないかと思われる、過剰な能力の試験室は、実際に、かなり多く目にします。
また、室内に有る全ての機器が、全部一斉に定格電力で働く事は、まず無いと思います。
そこで、一般的には、この定格に、稼働率を掛けて計算しています。稼働率は、その業務の内容により異なりますが、0.4~0.6程度で計算するのが一般的です。
経験的には、室内に有る機器の定格電力の合計の半分の容量で見れば、まず十分です。
他社の試験室をご利用のお客様で、故障の多発や、消費電力の多さに悩まれて、相談される事は良く有ります。ここで実際に試験室使用状態の発熱量を調べると、仕様書よりかなり少なく、明らかに、これは過剰設計だなと思われる装置が実に多いのです。
この様な装置を弊社の制御方式に改造、あるいは空調設備だけ交換した例が有りますが、改造すると、消費電力が、1/3~1/6に減少した現場が沢山有ります。
弊社独自のCSC方式の装置は、必要なだけしか冷却除湿しないので、もし間違えて熱負荷を大きく過剰に想定しても、実際に運転した状態で発熱が少なければ、その発熱に合わせて、冷却除湿量を減らします。
過剰な冷却除湿が無ければ、再加熱、再加湿量も少なくなり、極端に省エネになるのです。
各機器の稼働率が下がると、消費電力が低下するだけでなく、故障が少なくなるメリットも有ります。
毎年故障して業務が停止して、高額な修理費がかかっていた装置が、空調機を改造、交換する事により、かなりの長期間、故障しなくなります。
お客様から、修理の依頼では無く、5年間も無故障だが、このまま運転していて大丈夫だろうかと、問い合わせをいただく事も良く有ります。
5年以上の場合は、定期点検をお薦めしておりますが、故障していないので、交換部品がほとんど無いので、点検費も安くて済みます。
改造により、電気料金が大幅に下がっただけでなく、毎年かかっていた、他社の修理費より、5年目に行った定期点検費の方が安かったと、大変喜ばれております。
この省エネ化工事の実績は、ホームページの省エネの項目でご確認いただけます。