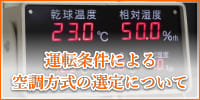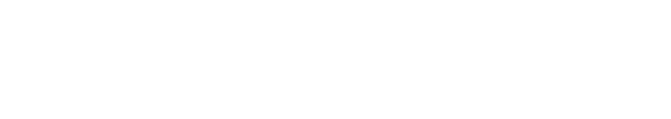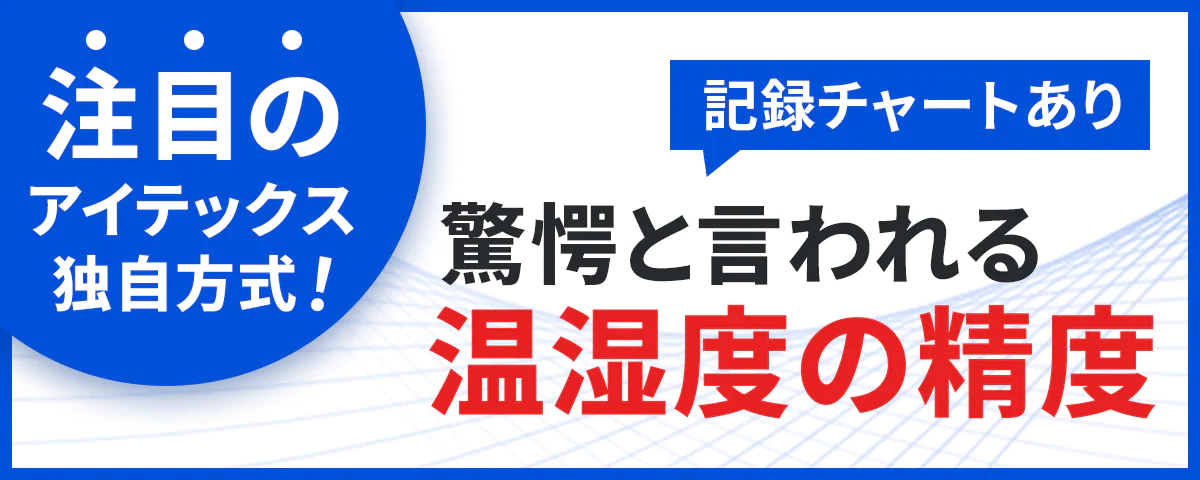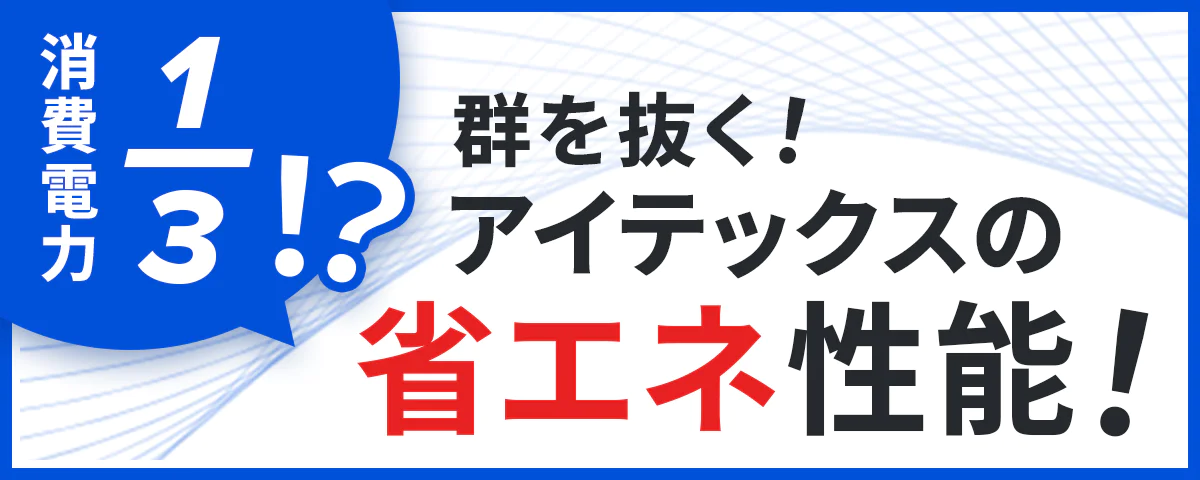加速試験とは
賞味期限や有効期限など、
時間経過による製品の品質変化を
実際より短い期間で実証する実験について解説します。
加速試験とは
食品には全て賞味期限が有り、薬品には有効期限が有ります。
たとえば、10年は持つだろうと想定しても、実際には10年間も待って製品の品質がどの様に変化しているか、調べている訳にはいきません。これでは時代の流れに遅れてしまいます。
これを何とか短い期間で実証しようとする実験を、加速試験と呼んでいます。
食品や薬品は、低温保存を指示されていなければ、一般家庭では、常温で保存する事になります。この製品が何年間品質を保てるかは、販売店の陳列棚や、家庭の引き出しの中を想定して、考える必要が有ります。
陳列、あるいは、保管する場所の温度が高ければ、保存期間が短くなるであろう事は、当然想定されます。
一般的には、これを加速試験で評価しています。これには、10℃2倍則、あるいは、10℃半減則と呼ばれる方法が有ります。
たとえば、夏季に平均で30℃になる様な保管場所で、100日間は変化しない製品でも、40℃の状態で保管すると、半分の50日で劣化すると言う考え方です。
60℃にすれば、30℃差ですから、保管期間は、1/2×1/2×1/2になり、60℃なら。13日間試験すれば、30℃で100日間保管したのと同じ状態になるであろうと考えます。
そんな物かなあと言う気はしますが、これを逆に考えると、長期間の安定保存をしたければ、保管庫の温度を下げれば良いわけで、食品関係では、低温の倉庫が利用されています。
お米も低温倉庫であれば、古古古古米になる迄、何年も保存できます。高く売ろうと、普通の倉庫に隠すと、夏季は40℃にもなり、穀蔵虫が発生してしまうのです。
お米を隠すのはやめましょう。
加速試験の内容を見ると、温度の規定だけで、湿度の規定が見当たりません。実際には、湿度もかなり影響すると思います。ビニール袋に入っている乾燥したお菓子類、例えば、おせんべいなどは、湿度の影響の方が、はるかに多そうですが、弊社で納入しているのは工業製品の試験室が多いので、一般的な食品に関する湿度の試験規定は良く判りません。
各社それぞれの規定が有って、それに基づいて検査をされている物と想定されます。
薬品関係は特別で、製薬会社に納入した試験室では、40℃/75%で6ヶ月の保管試験をされています。この間に温湿度が絶対に乱れない事を要求されます。
薬品関係の試験室は、かなり厳しい温湿度条件ですし、6ヵ月以内には絶対に故障しない、あるいは故障時には、即刻修理して、現状復帰ができる試験室が要求されます。
40℃/75%の高温多湿の試験室では、冷却する必要はほとんど無い様に思われますが、近年の夏季では、外気が40℃を超える事が有ります。また、多湿にする為に、加湿器でお湯を沸かすと、この沸騰した蒸気熱で室温が上昇しますから、冷却はどうしても必要になります。
室温が上昇しない様にするには、冷凍機を使用して、冷却してから加熱する事になります。
すると、同時に除湿をしてしまう事になります。温度だけを下げる事は出来ないのです。
この様な高温多湿の条件では、設計を誤ると、どんどん冷却除湿して、どんどん加熱と加湿して、空調機内で冷却除湿と、加熱加湿を喧嘩させるような装置になります。
これでは、消費電力が大きく、故障の多い装置になってしまいます。
高温多湿の条件では、ほとんど冷却除湿する必要は無いのですが、わずかに冷却する為に、冷凍機を使用する事になります。小さな能力の冷凍機は市販されていないので、やむなく1馬力程度の小型冷凍機を採用する事になります。すると、高温多湿の条件を得たいのに、大幅に冷却除湿してしまうので、加熱ヒーターと加湿器の稼働率が高くなります。
この様な装置では、消費電力が大きくなり、加湿器の故障が多発します。
弊社では、この様な装置の場合、弊社独自のCSC方式で、冷凍機の能力を出来るだけ抑えております。また、空調機内に2台の加湿器を組込んでおり、これを軽く働かせ、運転中に交互に洗浄して、加湿器の故障を防止しております。
この方式は、万一の加湿器の故障発生時には、片方だけの運転でも湿度条件が得られますから、加湿器を修理する迄の間も、温湿度条件は乱れません。
加速試験を行う場合には、実験途中の加湿器故障による湿度低下を心配する必要が無く、加湿器の交換は簡単に出来る様に工夫しておりますので、修理や交換も、短時間で出来ます。弊社CSC方式には、この様なメリットが有りますから、とても喜ばれております。
CSC方式の詳細は、恒温恒湿室の項目で詳細に説明しておりますので、ご参照下さい。
また、高温多湿の条件では、湿度センサ自身が吸湿して、感度が低下する場合が有ります。85%で運転していたら、センサの感度が低下して、いつの間にか、湿度調節計の指示は85%なのに、室内は100%になってしまい、壁に結露して、床がプールになってしまった例を、過去に数件ですが、経験しております。
湿度を上げたり、下げたりする場合は、低湿時に乾燥するので、ドリフトは発生しません。高温多湿の条件で、長期間の連続運転をした時にだけ、時々発生しております。
このセンサを、メーカーに送り、調べてもらった事が数回ありますが、輸送中に乾燥してしまうからか、全てが異常無しで返されています。
この様なトラブルを経験して以降、高温多湿の条件では、湿度センサを加熱して、測定値を補正するタイプのドリフトしない湿度センサを採用しております。この湿度センサを採用して以降は、室内に結露したり、床にプールが出来る事は有りません。
但し、このタイプのセンサは輸入品にしか無く、非常に高額です。高温多湿で連続運転する場合は、湿度センサを節約すると、室内の床に、プールが出来てしまう可能性が有ります。
高温多湿の条件で、連続運転する場合は、この湿度センサをお薦めしております。
この他に、工業製品では、ヒートショック試験が有り、高温と低温を繰返して、製品の信頼性をテストされている場合も有ります。